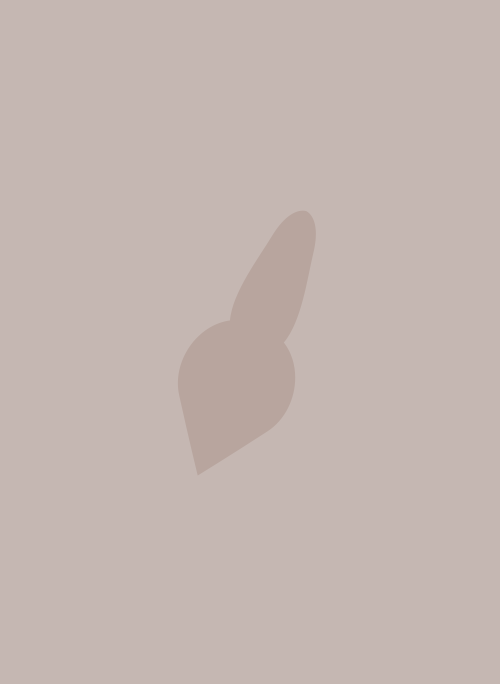少女の白い首には、先程まで強く締め上げていた自分の指の痕が痛々しく残っていて、男は、何故だか無償に自分自身に腹がたって
少女の側まで歩いていき
少女の頬に触れた。
無感情なままでこちらを見つめる少女に、なんとも言えない感情が沸き上がってくる。何故だかわからないが、彼女に名前をつけようと思った。
「さくら。」
少女が、瞬きして首を傾げる。
「キミの名前だ。」
少女の顔に驚きが浮かんで、そして、微笑んだ。
「はい!」
少女の側まで歩いていき
少女の頬に触れた。
無感情なままでこちらを見つめる少女に、なんとも言えない感情が沸き上がってくる。何故だかわからないが、彼女に名前をつけようと思った。
「さくら。」
少女が、瞬きして首を傾げる。
「キミの名前だ。」
少女の顔に驚きが浮かんで、そして、微笑んだ。
「はい!」