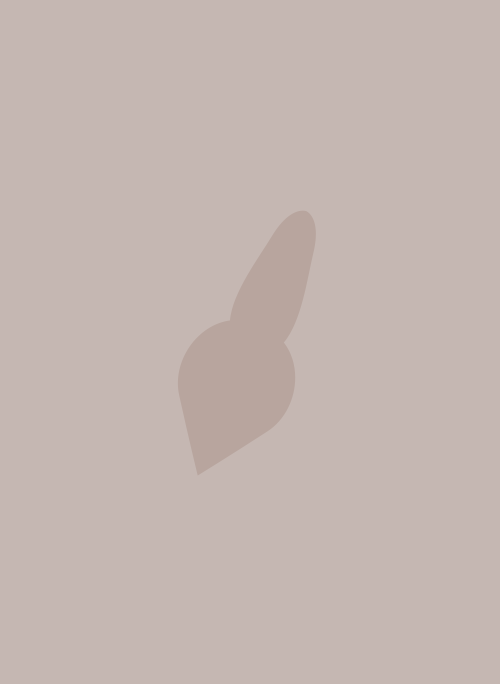当たり前だけど、別に、ナツのことを母親だと思ったことは、一度もない。
でも、ナツが俺にしてくれていたことは、俺がナツにさせていたことは、母親とそんなに変わらなかったのかもしれない。少なくとも、ナツにそう思わせてしまうことだった。
とにかく、俺がナツに甘えていたことは、確かだったんだ。
ナツは優しいから。俺と違って、大人だから。
「おい、沖田」
「はい?」
バイト中、今日もまた同じシフトの大川先輩が俺に話しかけてくる。
「お前なぁ、死んだ顔やめろよ。今はまだ客少ないけど、もう少ししたらピークなんだからな。客の前でまで、んな顔すんなよ」
「はあ……はい」
注意を受けて、俺は頷いた。
でも、こんなこと言ったらだめだけど、やる気になれない。笑うなんて、したくない気分だ。
「何だよ、落ち込んでんのか?」
俺の様子を見て流石に気付いたのか、先輩が言った。
「はあ……まあ」
落ち込んでるなんてもんじゃないけど、俺は曖昧に濁した。
「どーせお前のことだから、また彼女絡みのことで落ち込んでるんだろ。何なんだよ、今度は。つうか、昨日は彼女のとこに泊まるとかどうとか散々言ってたんじゃねえのか」
その言葉で、俺は昨日までのことを思い出した。
昨日は本当に楽しみで、嬉しくてしょうがない日だった。そして、すごく幸せになれる日のはずだった。
なのに実際は、ナツを傷つけて、ナツに拒絶されて……
「はぁー……」
俺の口からは大きなため息が出た。
こんなはずじゃなかったのに……