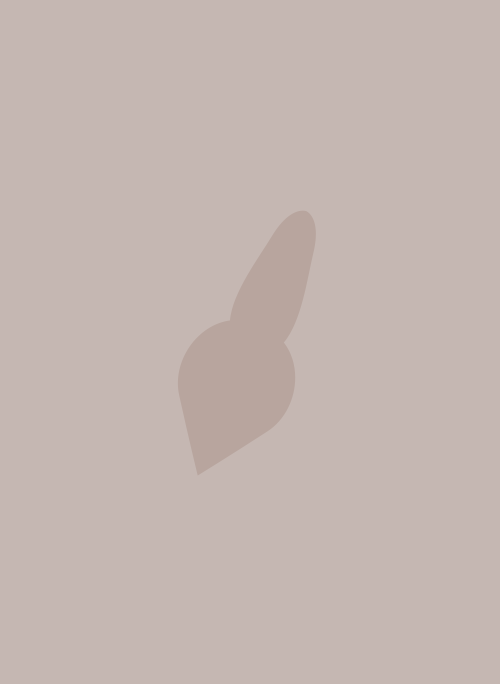本当に情けない。
ナツを困らせて、ナツに呆れられて……
俺って、ナツにとって、何なんだろう……
「ナツ。俺ってナツの彼氏だよな?」
たまらず俺はそう言っていた。
「何言ってんの? そうじゃないの?」
ナツは更に呆れた口調になっていた。
「だって……何か違うじゃん。メシとか、いっつもナツが当たり前のように払うし」
俺が言うと、ナツは目を丸くしていた。
「確かに、俺、金ないけどさ。さっきみたいに俺が出すって言っても、断って、ナツが払っちゃうし。……それに、デートの時、手も繋いでくんないし。今も俺側の手で鞄持ってるし」
「えっ……」
「ナツって、そういうの嫌いなの?」
本当に格好悪い。
男のくせにこんなこと気にして、彼女の前でグチグチ言って……
これじゃあナツに呆れられてもしょうがないかもしれない。
「えっ……あ、別にそういうわけじゃ……今までそういう習慣なかったから……」
今度のナツは呆れてる様子じゃなかった。
少し戸惑った様子で、下を向いている。
「……嫌ってわけじゃない?」
俺はナツの顔を覗こうとしてみる。
よくは見えなかったけど、ナツの顔は赤いようだった。
「うん」
ナツは小さく頷く。
「じゃ、繋ご?」
そう手を出すと少し照れくさかった。
改めてこう言って手を繋ごうとするのは、初めてだったかもしれない。
少し間を置いて、ナツが、そっと手を出して、ぎこちなく俺の手を触って握った。
「へへっ」
思わず俺は笑ってしまった。
ナツの手の感触を確かめるように握り返して、指を絡めた。
ほんの少し照れくさくて、でもそれ以上に嬉しかった。
ナツを見て見ると、ナツも少し照れくさそうにはにかんでいた。
手を繋いだだけで、ナツがすぐ近くにいるように感じた。今まで見ていたナツと違う角度でナツを見れるように感じた。
そしてそのナツは、いつも以上に愛しかった。