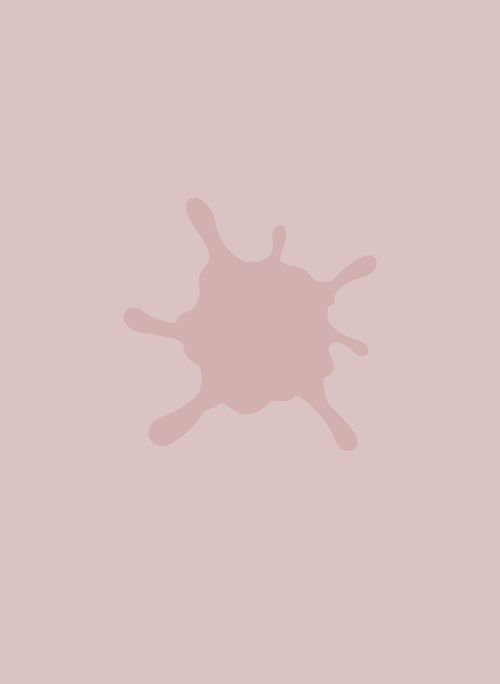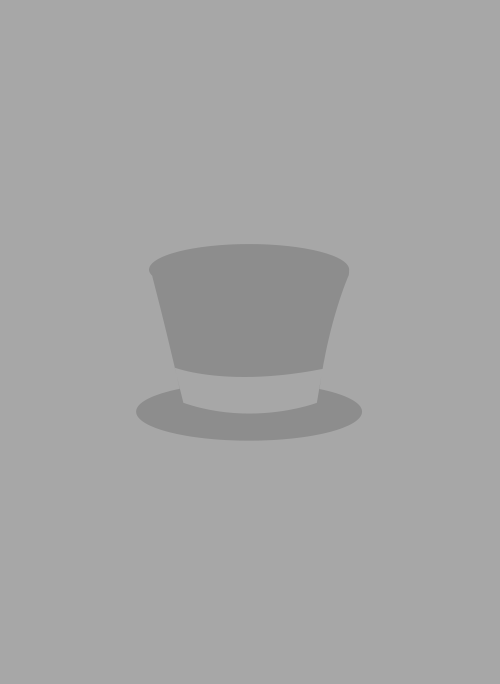微笑む「少女」。だがその横顔には薄く影が挿していた。口をつぐむ憲治。どんな憂いよりも寂しい笑顔。それは憲治の目の前にあった。そして。
「…生きでけれ…。」
「…?」
「少女」がそう言った。そう思った。「少女」の桜色の唇は露ほども動いてはいない。憂いを滲ませた「少女」の言葉は、音を成してはいなかった。憲治の鼓膜を震わせることはなかった、その「少女」のつぶやきは確かに憲治の心の中でうずいたのだったが、その言葉の意味を理解するには及ばなかった。それほどに些細な胸騒ぎでしかなかった。
「…生きでけれ…。」
「…?」
「少女」がそう言った。そう思った。「少女」の桜色の唇は露ほども動いてはいない。憂いを滲ませた「少女」の言葉は、音を成してはいなかった。憲治の鼓膜を震わせることはなかった、その「少女」のつぶやきは確かに憲治の心の中でうずいたのだったが、その言葉の意味を理解するには及ばなかった。それほどに些細な胸騒ぎでしかなかった。