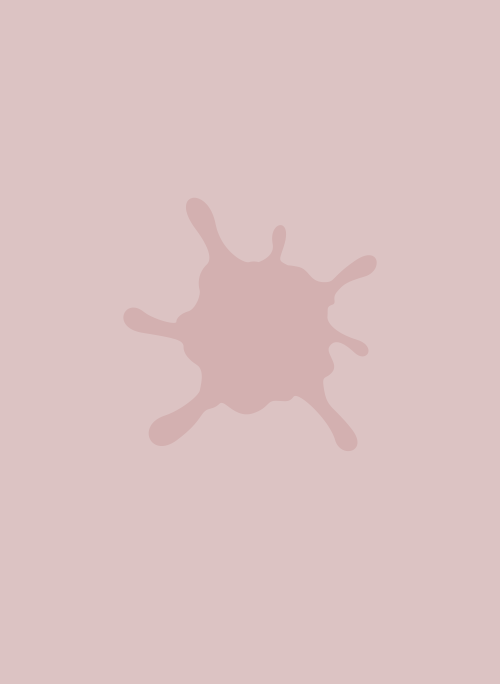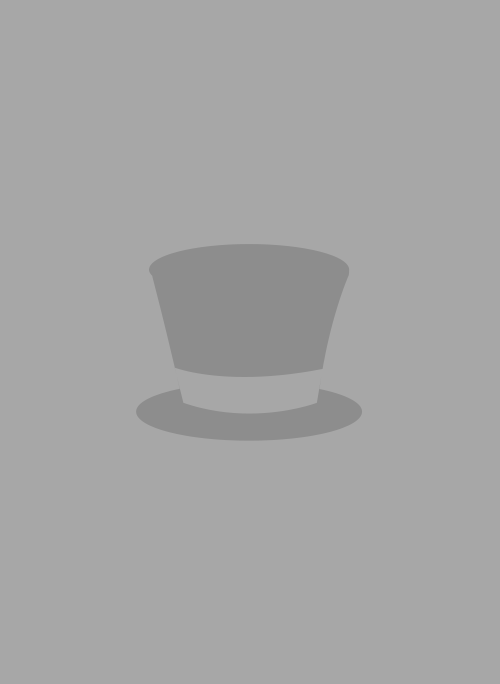「あ、あのぉ…、」
さきほどまでの勢いを、あっと言う間に消されてしまった憲治にとって、胸の中で自分を見上げるこの美少女のとった行動は「好都合」どころか、「恐怖」に等しかった。憲治の時間が凍りついた。
まるで「空気」を抱いている感触。体温だけがそこに存在している儚(はかな)さ。しかし、憲治の背中に回した「少女」の腕の細さといい、まだ幼い、それでいて生意気に「女」を主張し始めた胸のふくよかさといい、何もかもが曖昧でありながら、なおかつ存在を許されている。それが、その「少女」の、今憲治が感じることの全てだった。
さきほどまでの勢いを、あっと言う間に消されてしまった憲治にとって、胸の中で自分を見上げるこの美少女のとった行動は「好都合」どころか、「恐怖」に等しかった。憲治の時間が凍りついた。
まるで「空気」を抱いている感触。体温だけがそこに存在している儚(はかな)さ。しかし、憲治の背中に回した「少女」の腕の細さといい、まだ幼い、それでいて生意気に「女」を主張し始めた胸のふくよかさといい、何もかもが曖昧でありながら、なおかつ存在を許されている。それが、その「少女」の、今憲治が感じることの全てだった。