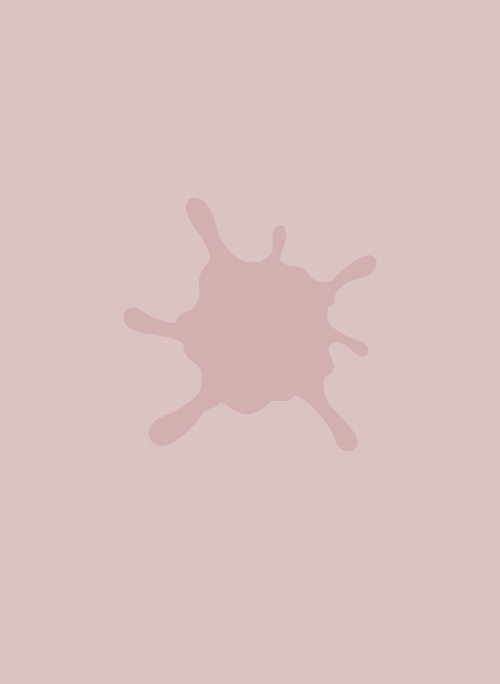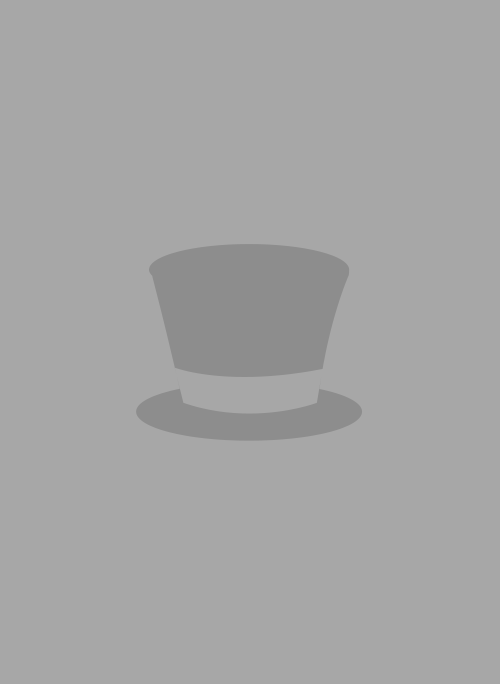その度毎に、世間体が保てた安心感と、一番嘘を吐いてはいけない相手=自分に、嘘を吐いている自分への呪いが入り混じっていた。
何一つ自分の中に確かなものを持てぬまま、流されるままに生きている今、自分の吐いた嘘の重さが軽薄な振舞の奥底に淀んでいる。
憲治の周りではしゃいでいた憧子が、ふと、静かにもう一度言った。
「…飛んだよ、憲治さん。」
そして憲治の顔をのぞき込み、
「うれしぐ、ねなだが?」。
憲治はちょっと黙っていたが、ため息とともに口元を緩ませた。
何一つ自分の中に確かなものを持てぬまま、流されるままに生きている今、自分の吐いた嘘の重さが軽薄な振舞の奥底に淀んでいる。
憲治の周りではしゃいでいた憧子が、ふと、静かにもう一度言った。
「…飛んだよ、憲治さん。」
そして憲治の顔をのぞき込み、
「うれしぐ、ねなだが?」。
憲治はちょっと黙っていたが、ため息とともに口元を緩ませた。