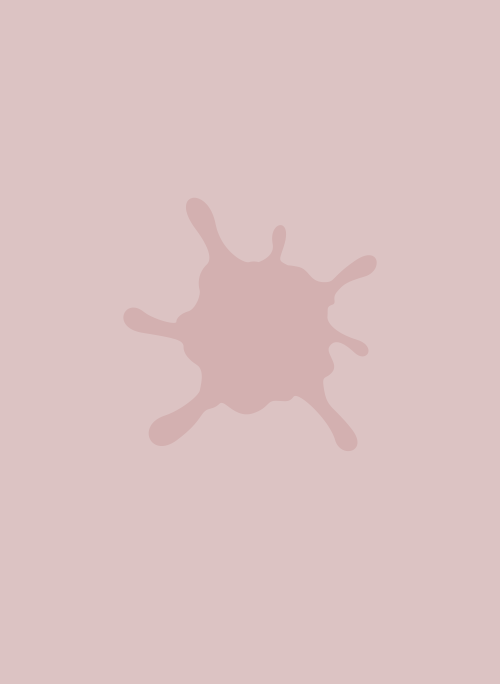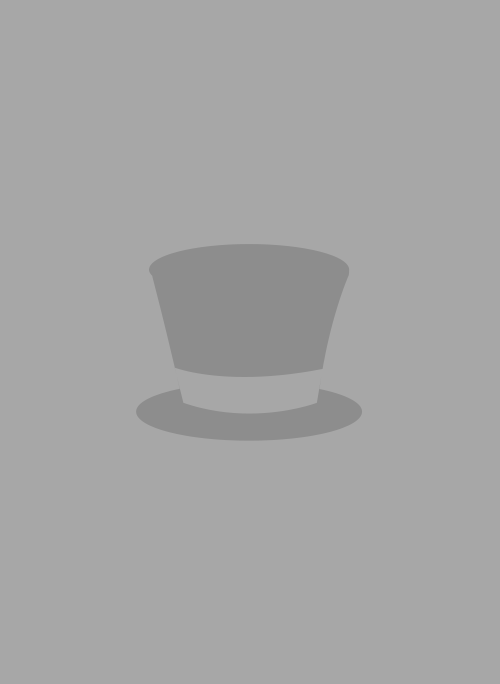たとえ、その先にある結末が生命を拒絶するものだとしても。
「はあ…、」
憲治は月を見上げる。
「皆がするような、普通の…、」
「恋愛」の言葉を口にすることが出来なかった。抵抗がある。現実感が無い。何もかも、信じられなくなっている自分に気づいた憲治。まるで、もう死期が近いと決めつける口調で、
「…は、出来なかったなぁ…」。
その時、桜がざわめき、稲穂の波が月の光を受けて輝いた。もう、憲治には分かっていた。「少女」だ。
「はあ…、」
憲治は月を見上げる。
「皆がするような、普通の…、」
「恋愛」の言葉を口にすることが出来なかった。抵抗がある。現実感が無い。何もかも、信じられなくなっている自分に気づいた憲治。まるで、もう死期が近いと決めつける口調で、
「…は、出来なかったなぁ…」。
その時、桜がざわめき、稲穂の波が月の光を受けて輝いた。もう、憲治には分かっていた。「少女」だ。