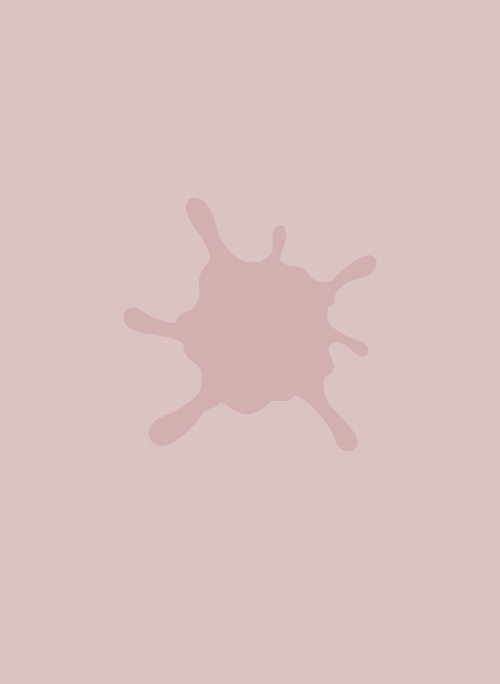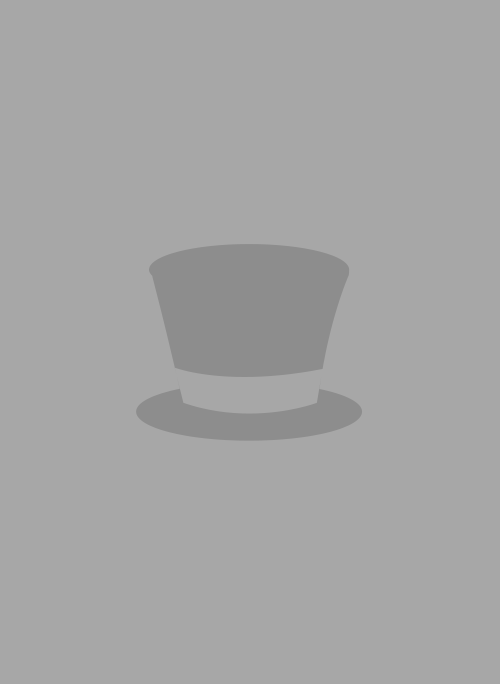こいつらと同じ中学生の頃、まだ熱い何かを追い続けた季節があった。今は潰えたはずの青くさい純情とやらを信じていた時代があった。好きであり続けさえすれば、全ての願いは叶うはずだと思い込んでいた。飛行機だって、そう、女の子だって。
「恋」の一文字に震えながら、誰かを惟い続けられたあの日。そして、遠い輝きに心奪われながら、大きく広げた指先からこぼれ落ちていった惟い。淡い、惟い。
馬鹿なことを、と憲治は自分を笑った。
「恋」の一文字に震えながら、誰かを惟い続けられたあの日。そして、遠い輝きに心奪われながら、大きく広げた指先からこぼれ落ちていった惟い。淡い、惟い。
馬鹿なことを、と憲治は自分を笑った。