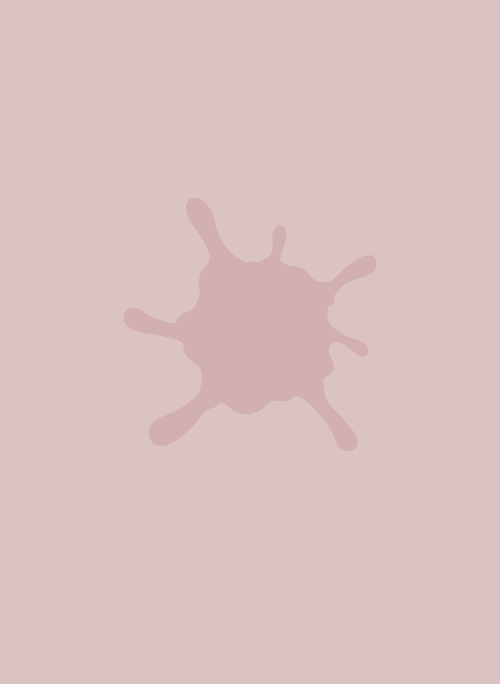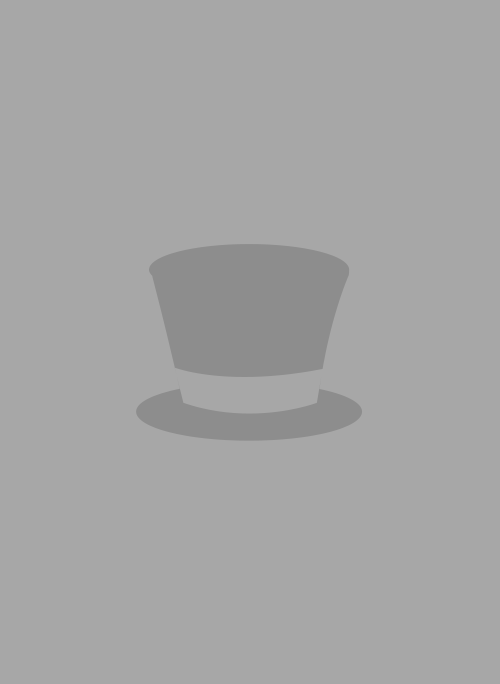「先輩…、会いたかったですぅ…、」
体を震わせ、声を上擦らせながら自分の背にすがる「聖菜」を、憲治は複雑な想いで受けとめる。
彼女が自分を慕ってくれていたのは確かだった。そしてあの頃、女の子には全然縁の無かった自分を、「聖菜」は好きだと言ってくれた。
しかし、「あの日」からの憲治には、これはある意味で拷問に等しい。
体を震わせ、声を上擦らせながら自分の背にすがる「聖菜」を、憲治は複雑な想いで受けとめる。
彼女が自分を慕ってくれていたのは確かだった。そしてあの頃、女の子には全然縁の無かった自分を、「聖菜」は好きだと言ってくれた。
しかし、「あの日」からの憲治には、これはある意味で拷問に等しい。