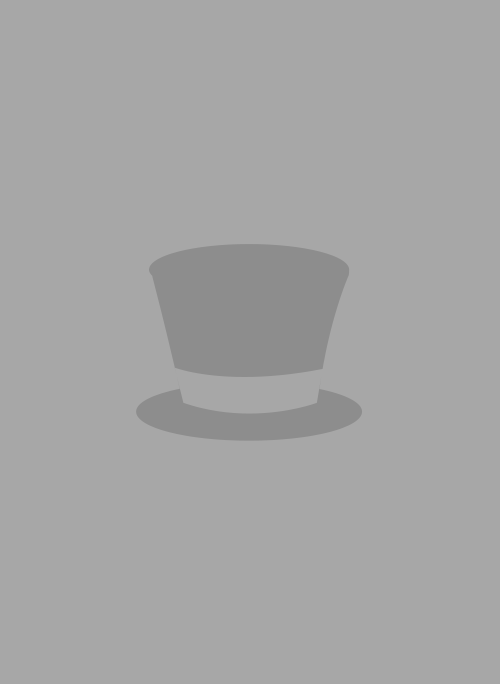「君が借りてたんだ」
「えっ?」
話が飲みこめず首をかしげる。
彼は「ああ」と言って説明してくれた。
「父さんの本なんだ、これ」
「お父様の?」
おもむろにページをめくり進め、満足げにうなずくと、本を閉じて背表紙を指差した。
「ぼくの名前は縁司。で、この著者は縁司郎(えにししろう)、父さんの名前。昔、1冊だけ本を出版したことがあって、この図書館に寄贈したってことを少し前に初めて教えてもらったから、それ以来ずっと探していたんだ」
「そうだったんです、か」
驚きは、それほどでもなかった。
私がたくさんの蔵書の中からこれを選んだのは、単なる偶然ではなかったから。
彼に出会って、観察を始めて名前を知ったある日。
図書館で背表紙を何気なく指でなぞりながら眺めていたら、たまたま1冊の小説が目に留まった。
それが、彼の名前にそっくりなこの「縁司郎」という著者の小説だったのだ。
半ば衝動的に借りた本だったけれど、中身はロマンチックな恋愛小説で、内容がとても気に入ったために借り続けていた。
もちろん、彼の父親だとは露知らず。
どうりで名前が似ているわけだ。
彼が毎日図書館に通って国内小説の棚ばかり見ていたのも、これを探していたからなのかと、ひとりで納得した。