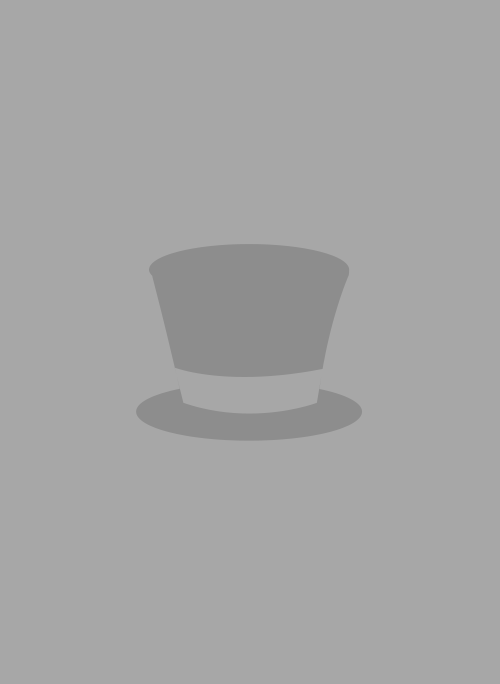「え、な、なんです、か……?」
かろうじて声をひねり出すと、彼は「これなんだけど」とブレザーの内ポケットから写真を取り出した。
「はい、これ」
私の右手首をそっと持ちあげ、彼は写真を手のひらに乗せてくれた。
ずっと冬風に晒していた私の手に触れた彼のそれは、カイロのように温かく、ジンジンとした感触に包まれた。
その何気ない行為は、けれど私が初めて父親以外で経験した、異性との接触でもあった。
嬉しさからか、驚きの連続からか、待機中の涙がふと溢れそうになる。
私は顔に力を入れた。
まだ場違いだから、と。
「君が写っているやつ」
「えっ……」
見ると、私がエキゾチック・ショートヘアーの顎下をくすぐっている写真だった。
端のほうで慰み程度に写っているものだと思ったら、写真の中央にメインとして私がいた。
このずんぐり胴体の猫は確か、彼が公園で見つけて、
「野良にしては高級そうな奴だな」
と言いながら、顎の下を撫でたり写真を撮ったりしていたときのだ。
彼が去った後、見ていた私が近づいて同じように触って、「間接握手だ」なんて他愛のないことを考えながら、ささやかな幸せを感じていた瞬間の。
彼が、私の真意(ついて回っていたこと)を知っていたか否かは分からない。
けれど、とにかく私には、顔なんて言わず全身の毛穴からも火が出るほど恥ずかしい写真だった。
そうして、耳に火照りを覚えているとき、彼が唐突に言った。