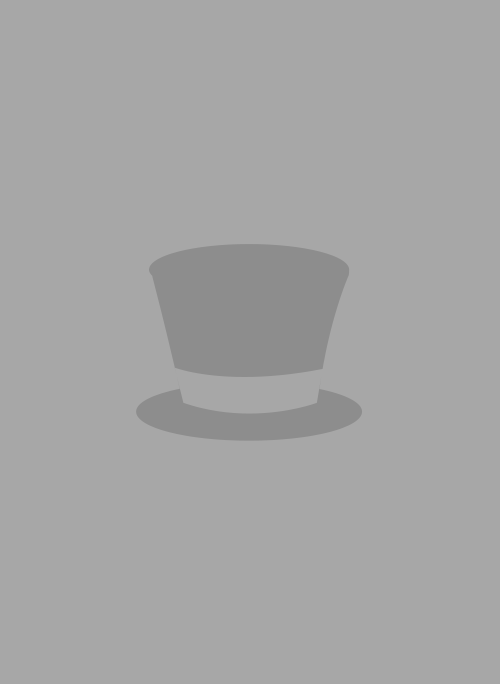一目惚れから1年後、16歳の冬。
午後の下校途中、下手な尾行をする新米刑事のように、彼の後姿を隠れたつもりで追いながら公園へ入ったときだった。
「ねえ」
彼が突然振り返り、プラタナスの後ろで様子をうかがっていた私のほうへ近づいてきた。
霜交じりの砂を踏む音が少しずつ大きくなるにつれて、私は後ずさりもできず、起きながらにして金縛りという珍しい状態に陥ってしまった。
蛇に睨まれた蛙、社長に呼び出された平社員、母に睨まれた父(私の家族だけ?)。
例えはともかく、大好きな人から何を言われるのかと怖くなり、取り急ぎ涙の準備だけを整えた。
姿がどんどん大きくなり、吐く息の行方まで見える距離で彼は立ち止まった。
ほとんど目の前だ。
白い息を一度下に吐いた彼は、私と視線をつないで言った。
「もらってくれない?」
いつも横や後姿ばかりを見ていた私は、そのとき初めて至近距離で、しかも正面を向いた彼に声をかけられ、ひどく動揺していた。
トランポリンで遊ぶ子供みたいに、無秩序に跳ねる鼓動のせいで、身体がドクン、ドクンと震動するような感覚を覚えた。
視界も心なしか、震動に合わせて小刻みにブレているようにも見える。
準備していた涙に、私は必死に待機を命じた。
まだ様子を見るから、と。