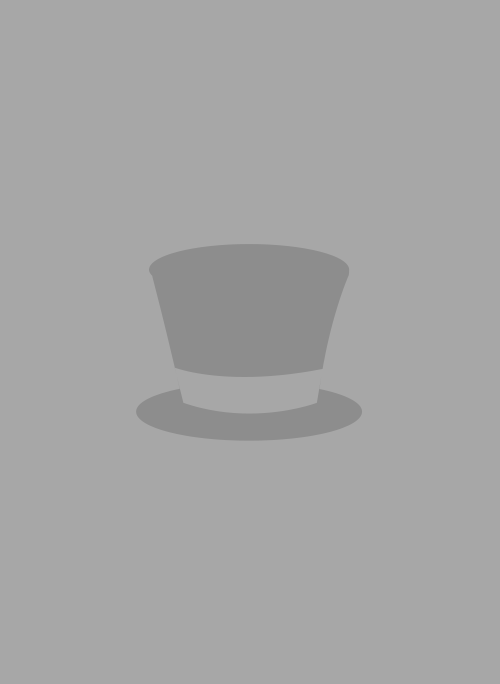「もしもし。ああ、ぼくだ……商品が?了解。じゃあ今からそっちへ向かう」
手短に話して電話を切った市村さんは、バツが悪そうな表情でこっちを向く。
「お仕事、ですよね?」
会話の内容から、事情を察した私が先にたずねた。
「はい。新規開発中の商品が完成したから、来てほしいということで……」
「あ、いいですよ。私に遠慮せず、お仕事へどうぞ」
イタリアン、と言われてなければ、少し残念なところだけど、今回は心底ホッとしていた。
「すみません。引っぱり回した挙句に、ランチをご馳走できなくて」
「平気ですから。そんなに謝らないでください」
「……はい。じゃあ、図書館までお送りします」
「お願いします」
行きとは違い、帰りの車中は重苦しい雰囲気が包みこんだ。
申し訳ないと思っていることが伝わってきて、私はあまり苦にはならなかったけれど。
それよりも、イタリアンじゃなければ、このまま別れるのが残念だと思っている自分の心境の変化を理解することのほうで、精一杯だった。
デートみたいな行為が初めてで浮かれている、という理由だけじゃ説明がつかない。
浮かれていたのは最初だけだし。
途中からは、だんだん安心していたことは事実だから。
恋愛未経験者の私は、心の端っこで、自分を好きになってくれている人を好きになろうとしているのかもしれない。
そんなふうに感じていた。