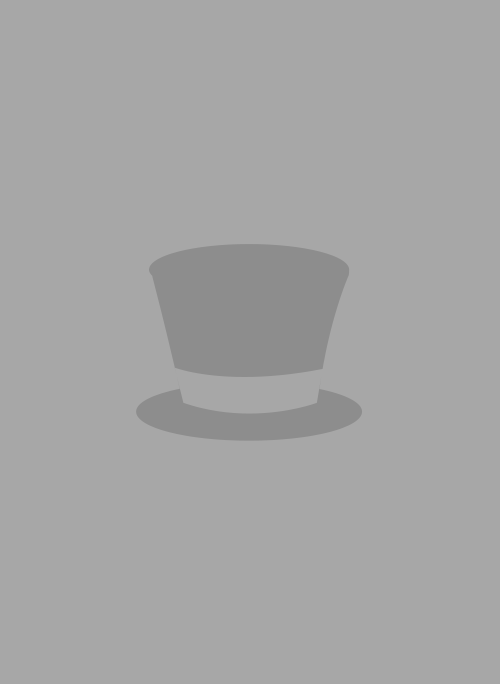「ふう、ありがとうございます」
大した残骸ぶりではなかったため、物思いに浸かる時間もなく片付けは終わり、彼が笑顔でお礼を言った。
「いえ。とんでもないです。これも仕事ですから」
杏奈ちゃんばりの赤ら顔を見られてはいけないと、私は肩上までの短い髪を駆使して耳を埋め、うつむいたまま大仰に手を左右に振った。
「助かりました。本当にどうも」
「あ、はいはい……」
「じゃあ」
「あ、はいはい……」
なんとも不甲斐ない醜態。
信号を発すべき絶好のタイミングで、全力をもって抑制してしまうなんて。
恥ずかしさを紛らわそうとすればするほど、態度もそっけなくなっていくし。
これでは、例え私のことを覚えていてくれたとしても、心証が悪いに決まっている。
媚態を示していたほうがまだよかった。
『手伝ってきなって。近づくチャンス!』
美咲の言葉が、頭の中でフェードアウトしながら繰り返し渦巻いていた。
きっと彼女も、私の体たらくに失望の眼差しを送っているに違いない。
そんなふうに自分を責めているとき、
「あの」
という声が耳に届いた。
顔を向けると、靴のつま先を床に叩いて感触を合わせている彼が、私を見つめていた。