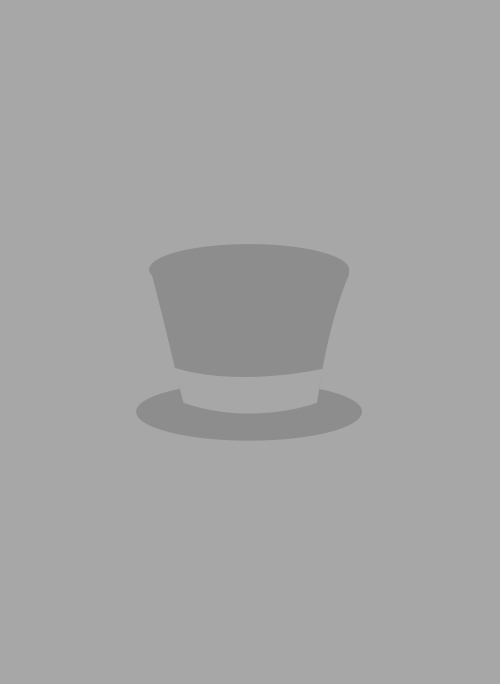「えっ……?」
思わず目を開けると、彼の顔が迫っていて、慌てて閉じ直した。
「そう。誰かさんのこと」
ふたりの唇が、重なった。
「……んむ……ぅ……ん」
味わう余裕もあり、それはさっきまで食べたチョコレートの甘みを帯びていた。
「甘いね、唇」
そっと離して、はにかむ彼。
「だったら、もっと――」
今度は私から、彼の口を塞いだ。
シートをたたくように、少しだけ強めの風が吹いた。
子供たちの余韻みたいだったケヤキの葉の音が、いつの間にか祝福の拍手に聞こえてきて。
心の中で、私は誰にともなしに「ありがとう」とつぶやいた――。
Fin……