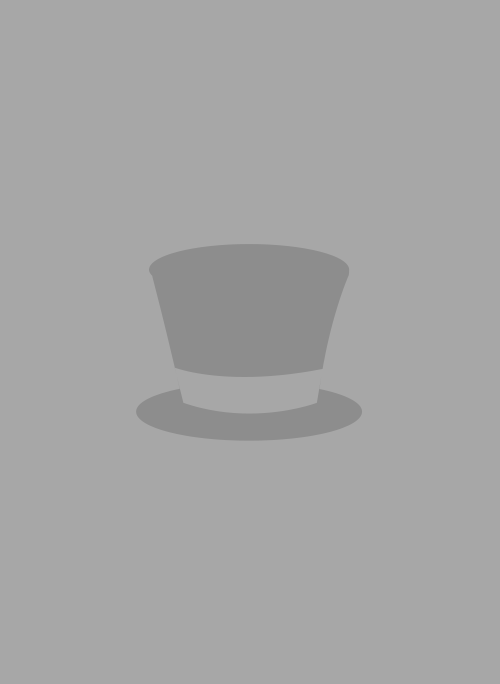「あ、あの……」
「ん?」
本を拾っていた手が止まり、視線がこっちに向いた。
ただでさえ、異性に声をかけるなんて勇気の要る作業なのに。
相手が彼となれば、その倍率と血圧は当然跳ねあがる。
憧れの歌手に会ったファンが気絶するのと同じように、私だってその気になれば、気を失えるんじゃないかという勢いだった。
失っても、なんらメリットはないけど。
「お、お手伝い、します……」
「ああ。どうもありがとうございます」
彼は覚えていないのだから、無理もないとはいえ。
「…………」
他人に話しかけるような口調に、どことなく寂しさがこみあげてきた。