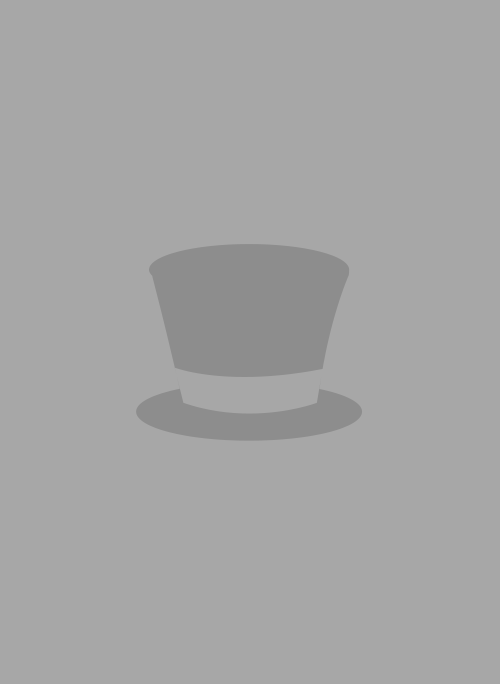「すごく新しいですね。楽しさのあるチョコだし」
「ありがとう」
「あの」
「うん?」
「もう1個、いいですか?」
「もちろん。全部君にと思って持ってきたんだから」
お言葉に甘えて、私はまたひとつをつまんで口に運んだ。
彼と過ごせる時間もさることながら、こういう高級なチョコレートに縁がなかった私には、それを独り占めできることも同じくらいの幸せだった。
「それで、新進気鋭のショコラティエさんは、どこで活躍する予定なんですか?」
懇切丁寧な講釈に耳を傾けつつ全部を食べつくした私は、舌で唇を舐めながらたずねた。
「うん」
「東京とか?」
「いや」
「じゃあ福岡や名古屋って大都市ですか?」
そこでもない、と彼は言って立ちあがった。
「ちょっと、外を歩かない?」
ドクン、と胸で不安の警鐘が鳴った。覚えのある鳴り方だ。
(もしかして)
二度あることは三度ある、という言葉が頭の中でツタ状になり、ボランティアを辞めると言われるときの既視感に絡みついた――。