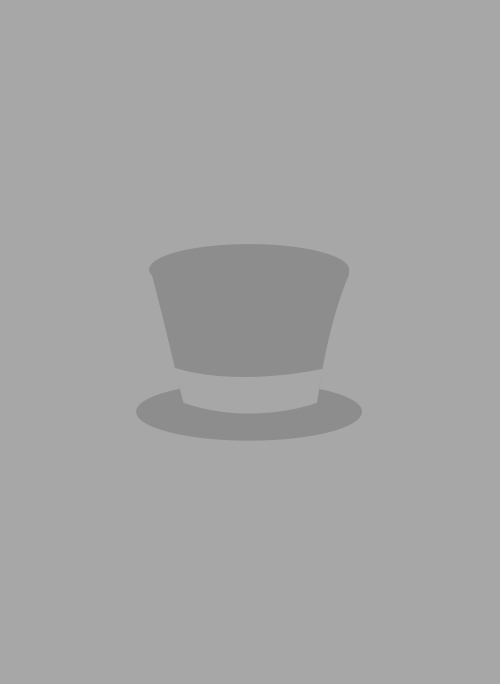「ああ。ろくに話をしたこともなかった人に、いきなり告白されたから驚いたろうに。でも美也子は、くしゃくしゃになった顔をハンカチで拭いてくれたよ。私のためにこんなに泣いてくれるあなたのことを、もっと聞かせてくださいって言いながら」
「なんだか――」
私の言葉を引き継ぐように、マスターは笑った。
「似てるだろ? 誰かさんと」
「すごく」
だからかな、と彼は私の頭を撫でた。
「雛ちゃんが店で大泣きしたときに確信したよ。この子は絶対に成就する、成就しないわけがないって。天国の美也子が、ふたりをちゃんと幸せに導いてくれるって」
マスターの言葉を聞くと、どうも涙腺が緩んでしまう。
聞き上手、話し上手とあるように、彼には泣かせ上手という特技があるみたいだ。
たちまち喉が鳴って口が焼けてきて、子供に戻ったように涙がこぼれてきた。
なんだか、すごく嬉しかった。
そして、こんなにも私のまわりに初恋にまつわる大きなエピソードを持った人が多いことに、改めて驚いてもいた。
類は友を呼ぶとは、よく言ったものだ。
「もう絶対離すんじゃないぞ、彼のこと」
「……はい」
「いい子だ」
マスターはもう一回くしゃっと撫で、「さあ、飲みな飲みな」と目尻に皺をたっぷり作りながら笑った。