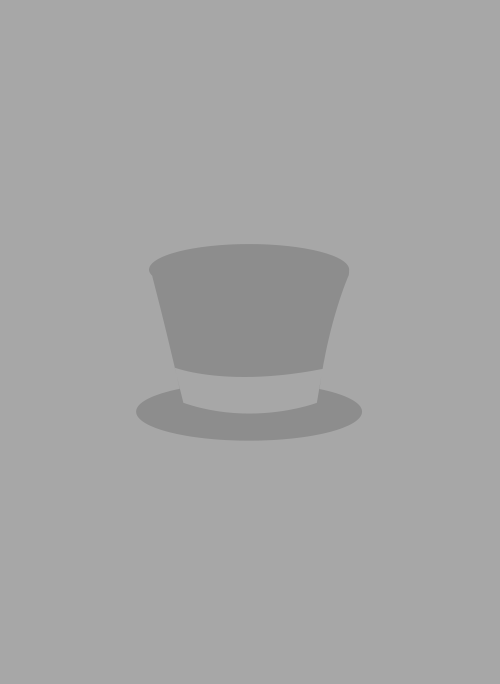それからしばらく近くの公園、つまり君と言葉を交わしたあの場所で雑談を交わしました。
彼が館長になったことや、父さんの本を君がまだ借り続けていて、たまにカウンターで眺めているみたいだ、ということなど。
恋人の気配もなく、まだ結婚もしていないということも。
他にも話は弾んで、いつしか館長の悩み相談になりました。
「図書館にもっと人を集めて、昔のような活気あふれる場所にできないものか」
館長は、空を見あげながら嘆息をついたので、ぼくは思いついたアイデアを口にしました。
それが、朗読会です。
あの図書館は、カウンター横にやけに広いスペースが余るように残っているけれど、なんだか空虚感を与えてしまうので、そこに子供たちに読み聞かせをするスペースを設けてみてはと。
空虚感も消せるし、子供に連れられて保護者も来るし、子供の読書離れも解消されるから一石二鳥にも三鳥にもなるプランじゃないですか、と。
館長は、ぼくの提案に興味を示してくれました。
ぼくはショコラティエの勉強のかたわら、常々いつか自分の店を作るときはこうしよう、ああしようっていうアイデアも練っていたので、プランニングには少し自信があったのです。
ただ、問題があると館長が言いました。
読み聞かせをしてくれるボランティアのことです。
必要最低限の人数でやっている小さな図書館なので、読み手はボランティアとしてやってもらうしかないけれど、今時そんなことを引き受けてくれる人なんているのかどうか、と言うのです。
だから、ぼくはすぐに立候補しました。
まだこっちでやることがあるけど、6月からならできます、と。
子供は大好きだったし、週末には十分な時間があったので。
何より、君の今を少しでも知ることができる――そう思いました。
今のぼくに気づいてもらえなくてもいい。
ただ、君が今をどう過ごしているのか、それがどうしても知りたかった。
これこそ、ぼくが朗読会のボランティアになった動機でした。