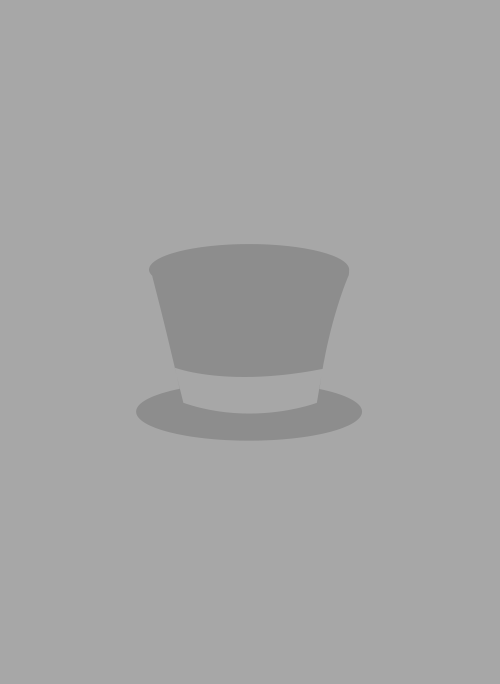「彼って、アンタのこと覚えてないの?」
ふと、美咲が肘で脇腹を小突きながら聞いた。
「うん。多分忘れてると思う――ていうか、昔すぎて今とは印象がずいぶん変わってるだろうし、気づこうにも気づかないって」
そうでしょう?というふうに、本を読み聞かせている彼に視線を送った。
無論、答えはない。
「直接本人に言ってみればいいじゃない」
「ダメ。絶対ダメ」
私は慌ててかぶりを振る。
「どうしてよ。こんなに近くにいるのに」
「覚えてなかったら、ぎこちなくなっちゃうし。これからも毎週土曜日の朗読会は続くっていうのに」
「でも、昔から彼を想って生きてきたんでしょう?15歳っていう、まだ愛の『あ』の字も分かりもしないような時期に、熱をあげて」
人見知りの私と違って、彼女は誰とでも仲良くなれる活発な女性だった。
人間界は、ことバランスで成り立つ世界。
太った人には細身の人、世話好きの人にはだらしない人、傲慢にはおおらか、そして消極的には積極的の組み合わせがなぜか多い。
摂理に相違なく、私は美咲に出会い、誘導尋問のように生い立ちを自白するハメになったものだから、彼とのエピソードも当然、話していた。