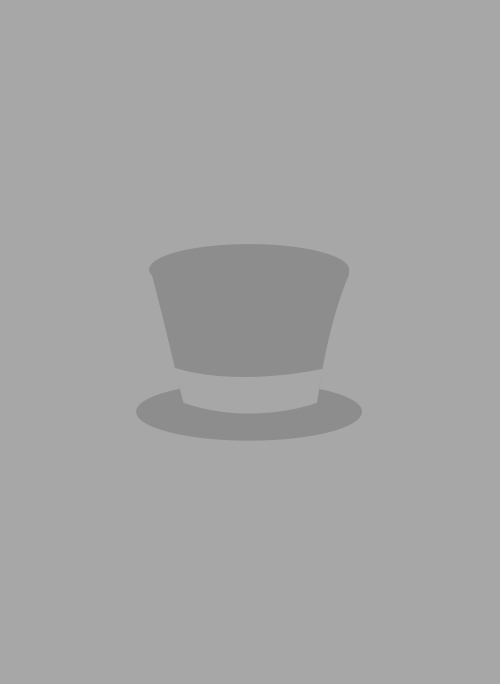「ねえマスター」
「ん?」
「私、大丈、夫か、なあ」
「もちろん。人ひとりのために、こんなに泣ける子なんだから」
マスターはスツールから腰をあげて瓶を戻し、前のめりになって私の頭をくしゃくしゃと撫でた。
実の父と同じような、大きな手だ。
「私、彼の、こと、好、きだ、から……」
「ああ。分かってるよ」
「でも、好きって、いう気持ち、しかなくって――」
私の言葉を最後まで待たず、彼は言った。
「いい。好きだけでいい」
揺らめく視界のまま顔をあげると、ぼんやり歪んで見える彼の顔は、たしかに笑っていた。
やけに自信ありげな表情には、妙に説得力があった。
「いい、の?」
「うん。いい。好きだけじゃ生きてけないって言うやつもいるけど、好きさえあれば、他のはあとからどうにでもなるもんだ。だけど、好きがなけりゃ、他に何があっても、どうにもならん」
「……うん」
「大丈夫。今みたいな気持ちがあれば、必ず成就する。おじさんが保証するよ」
「本当?」
根拠はなさそうだけれど、彼の言葉は一切の淀みがなかった。
「ああ。本物は、何も混ぜずにシンプルがベストだ。好きって気持ち以外に、何も混ぜる必要ない。まわりくどい台詞も、演出も、用意も要らない。今の雛ちゃんみたいな、泣けるほど好き、どうしようもないくらい好きって心こそ、何にも勝る魅力なんだから」
マスターは「絶対大丈夫だ」ともう一回だけ頭を撫で、笑いながらお皿を洗い始めた。
私はひとしきり涙を出し尽くして、心の膿を出し切ることに専念した。
まだ成就したわけではないけれど、ひとりでずっと抱えてきた苦しい気持ちが、幾分身体の外へ抜けていくのを感じて。
私は、涙の味がする喉にハワイコナをゆっくりと滑らせた――。