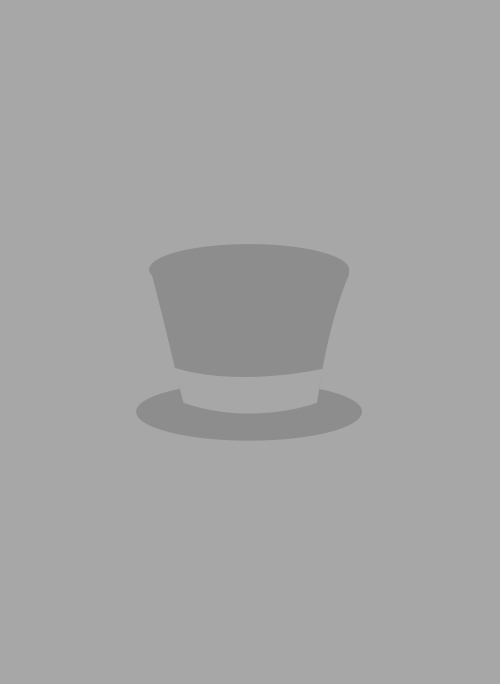今まで未練がましく引きずっていることを、誰より自分が罵ってきた。
私なんかが恋をするのが間違っているとか、資格がないんだとか、一番ひやかしてきたのは、私だった。
図星だからこそ、からかわれて腹も立てていた。
美咲や博美さんにあれだけ応援されながら、ときに温かく接してもらいながら、誰あろう私自身が、この初恋に反対票を投じていたことに、ようやく気づかされた。
自分でない誰かの声で叱られて、初めて立ち返ることができた。
立ち返ったら、泣けてきた。
唇が震え出す感覚がして、火の見櫓の半鐘のように、上下の奥歯がカチカチと音を立て始めた。
涙と熱い息が同時に溢れ、バッグに入っているハンカチを取り出す思考も及ばず。
私は、ただただ覚束ない震える指で、目元と鼻を叩くように拭った。
「雛ちゃん大丈夫かい?」
マスターは心配そうに近くのティッシュを箱ごとくれた。
2、3枚抜いて、目元を拭いながら、鼻をずずっと啜る。
自分でも無茶苦茶な顔をしていると思ったけれど、繕うそばから顔が崩れてしまい、収拾がつかない。
嗚咽が引かず、咳を何度もして、両手で鼻と口を覆いながらくぐもった声でたずねた。