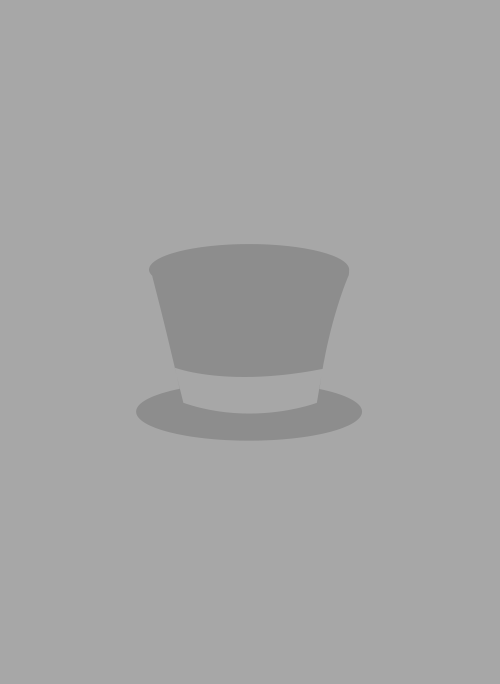「ふう……」
たしかにまだ本調子ではないらしく、力の抜けた身体でソファーへ横になった。
「パリ、行っちゃうんだ」
美咲との話を辿りながら、改めて事実を口にしてみた。
でも、どうしても自分とは違う次元の話に思えて、いまいち飲みこめない。
SF映画が苦手なところも、こういう狭い経験値とキャパシティに要因があるのかもしれない。
ただ、ひとつだけ痛感していることといえば、彼がまたも私の前から消えてしまうということだ。
毎週土曜日にも、二度と会えなくなること。
(今度も追わないの?)
天井に、問いを投げかけてみた。
私たちは『ビフォア・サンセット』のように再会を誓っていたわけでもなければ、親密に会話を延々交わしたわけでもない。
次の約束も、私の名前さえも告げぬまま静かに公園で別れただけの、ただの他人。
一方的に想いを寄せているだけの私が、一方的に運命だと思っているにすぎない。
彼の父親である、縁司郎の小説通り。
所詮は、偶然を別の読み方にしただけ。