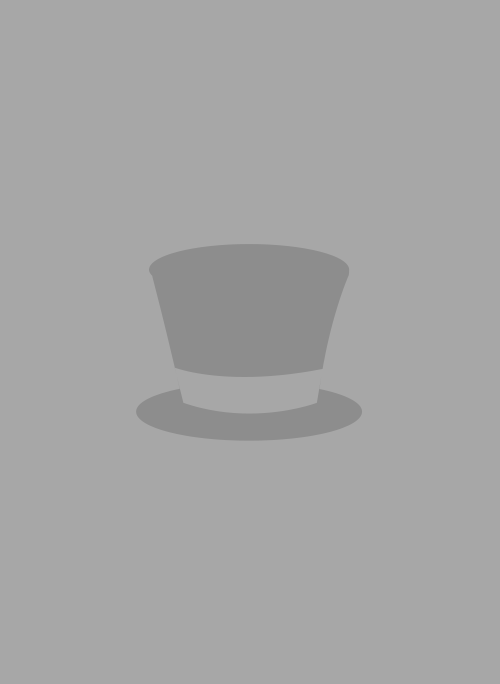「10年間も好きって気持ちが続くってさ、そうそうないんじゃない?散々口うるさく言ってきたけど、半分は博美さんと同じ。羨ましかった部分もあったのよ」
「羨ましい?」
「それだけ長い年月思うって、実は相当な情熱家の為せる業よ。本人は無自覚みたいだから、教えてあげるけど」
美咲は再びキッチンへ行き、自分の分のハーブティーも注いで持ってきた。
「私が、情熱家……ねえ」
「普通だったら、このハーブティーみたいに、時間が経てば冷める。冷めないとしても、別の気持ちにスイッチなりスライドなりさせると思う。博美さんみたいに」
「そういうものかなあ」
彼女の言葉が、ものすごく意外だった。
自己分析と真逆に位置しているはずの「情熱」という単語が、私自身の内面に息づいているなんて今まで一度も思わなかった。
臆病な情熱家?
矛盾しているんだか、いないんだか。
「それでどうするの?」
「どうするって?」
「あきらめちゃうのかどうか」
即答できずに口をつぐむ。
彼がいなくなった当初は、なけなしの希望でなんとか毎日を乗り切っていた。
直筆のメッセージと「いつかまたね」の言葉は、紛れもなく私だけのために向けられたものだと信じてもいた。
けれど、希望だけで何年もやり過ごすのは無理があった。
かといって、他の誰かで代替できない不器用な性格だと思っていたから「もうひとりで生きていくことにしよう。彼への想いは心の隅に寄せて、本と写真をよき思い出にして、身軽になろう」とさえ覚悟していた。