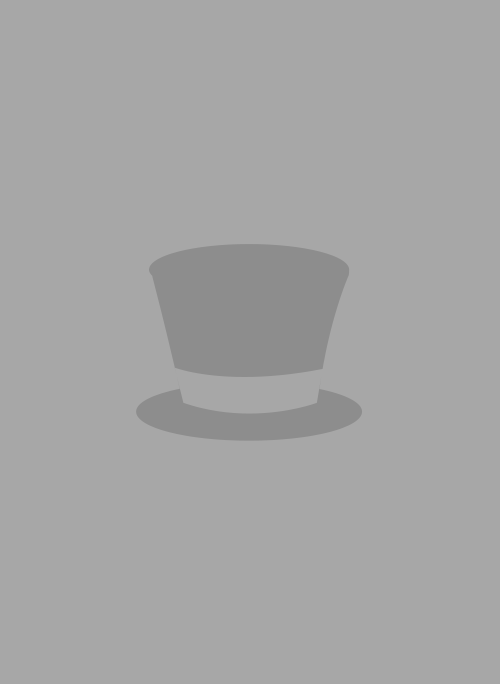「彼ね」
ふた口目を啜ったところで、美咲が口を開いた。
「うん?」
「アンタが倒れたとき、ものすごかったのよ」
「どういうふうに?」
「必死の形相で、カウンターに飛びこんできたんだから」
「そうなの?」
「あれは、いち職員を助ける人間の顔じゃなかった。特別な人を助けるときのそれだった」
「そう、かなあ……」
どこか腑に落ちなかった。
特別だと思ってくれているなら、どうして私に何も告げず辞めるだとか平気で言えるのだろう。
10年前を覚えてくれているなら、覚えているよ、とかなんとか話しかけてくれてもよさそうなのに。
忘れていて、改めて好きになってくれていたとすれば、仕方がないことかもしれないけれど。でも……。
「まあ、子供たちは終わったらすぐ帰っちゃうし、愛着があったからどうしても自分の口から伝えたかったのかもしれないけどね」
物思いを見透かしたように、美咲が苦笑いする。
「うん」
それでも、彼の気持ちが見えない。
正直そう感じていた。
自分のことを棚にあげてなんだけれど、他人と話すような言いぶりをしておいて、倒れたときは必死な形相になるなんて。
だったら、初めから伝えてほしかった。
美咲の言うように、仮に子供たちに言うつもりだったのなら、その前に。
マグを口につけたまま耽っていると、彼女が「にしても」と静かに言った。