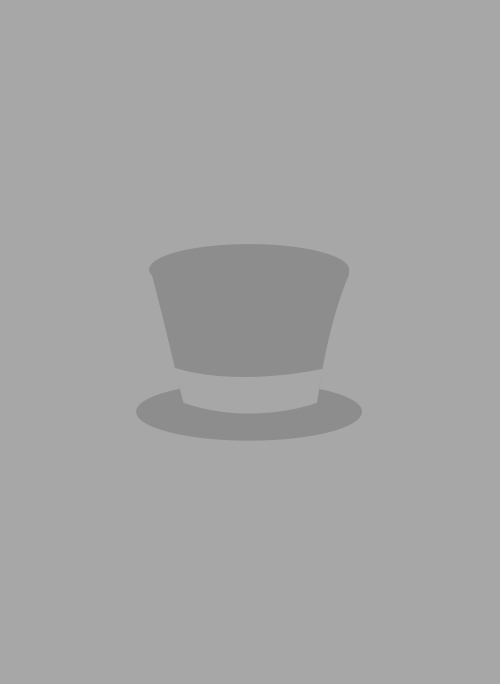バクン、と胸で銅鑼が鳴った。
「えー、お兄さんやめちゃうの?」
「次からお兄さんじゃなくなるの?」
子供たちがそれぞれ一斉に声をあげる。
美咲の心配そうな顔を目の端に捉えたけれど、私は応えられず、呆然と彼の話の続きを待った。
考えようにも、頭が働かない。
「そうなるね。お兄さんの朗読会は、今日でおしまいだよ」
バクン、バクン、と銅鑼がさらにふたつ。
「なんで辞めちゃうの?」
眉をハの字にした杏奈ちゃんが、たまりかねたように口を開いた。
答え次第では涙も辞さないという、診断結果を下される前の患者みたいな表情で、彼も若干言い難いといった感じを見せた。
「それはね――」
鮮明に覚えていたのはそこまで。
私はいきなり目を回した。
スツールに浅く座っていたため、バランスが崩れて椅子ごと音を立てて転げ落ちた。
多分、これ以上の情報を入れたら危険だと判断した身体が、自動的に私を『パニック・ルーム』に詰めこんだのだろう。
何かあってから、やむを得ず入るジョディー・フォスターとは大違いの、なんとも臆病な予防的措置として。
私は、失われる意識の隅っこで、
「雛子、雛子!」
誰の声とも判別のつかない叫び声を聞きながら「もう疲れた」と、ゆっくり力を抜いた――。