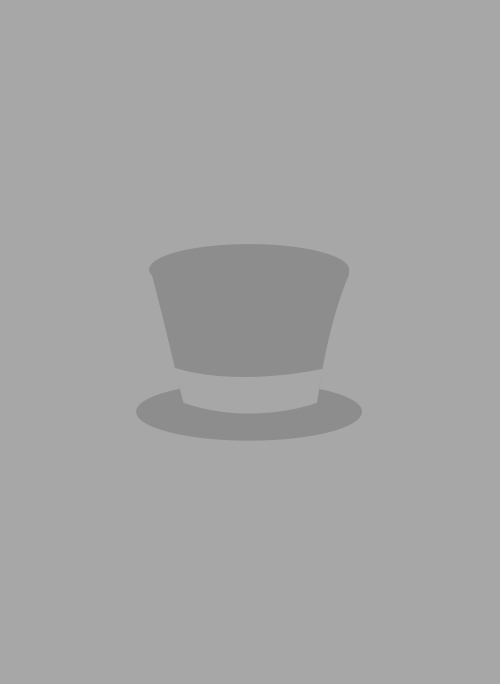2冊ほど読み終えたところで朗読会は終了。
特に変わったこともなく、子供たちが帰ろうとして立ちあがったとき、彼が突然「みんな待って」と声をかけた。
振り返る子供たちに手招きをし、それに応えてみんな彼のまわりに集まる。
嬉々としたざわめきとは違って、このときはどことなく困惑しているようなざわめきが浮かんでいた。
「なんだろう?」
「さあ……」
こっちが知りたい。
「ちょっと様子が変よね」
「う、うん……」
いつもと違うというのは、心を不必要に動揺させる。
加えて、今日はふたつも質問事項があったので、できればいつも通りでお願いしたいところなんだけれど。
不安げに見つめていると、彼がちらり、こちらに視線を送り、手を膝に乗せて腰をかがめた。
神妙な面持ちに子供たちも何かを感じ取ったのか、じっと聞き耳を立てるように視線を注いでいる。
「あのね、実は――」
言い淀み、子供たちを見回して咳払いをし、口を開く。
「来週から、お兄さん、朗読会に来られなくなるんだ」