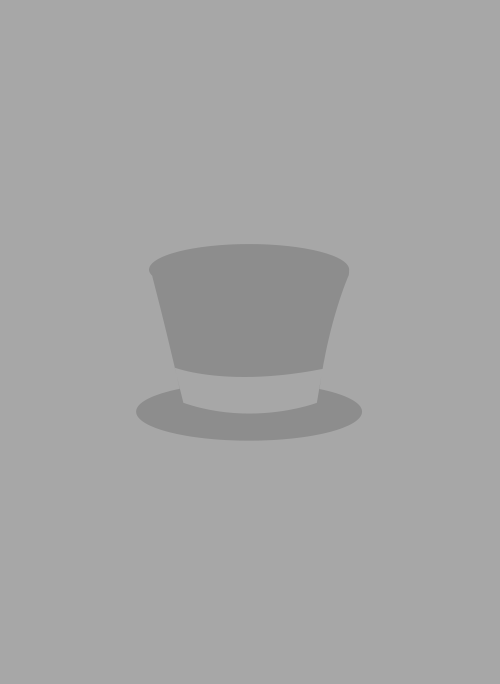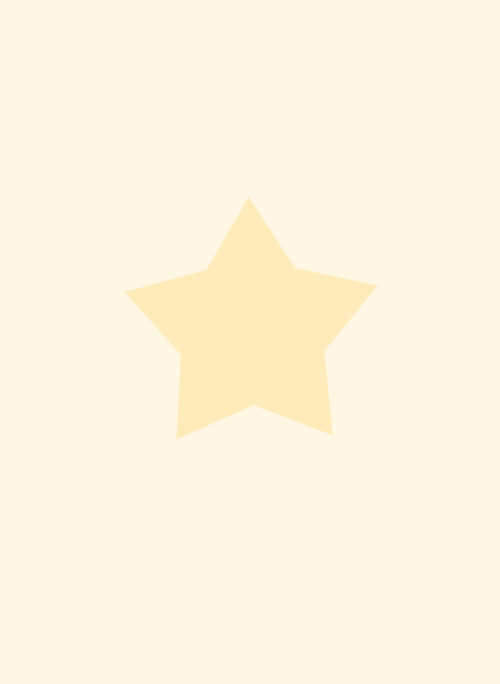次の瞬間、そいつは鼻血を噴き出して後ろ向きにひっくり返った。これがケンカに関しては、男子も陽菜に一目置いて恐れる最大の理由だった。陽菜は腕を後ろに振るとか腰をひねるとか、そういう事前のモーションが全くない状態から渾身の力がこもったパンチを自由自在に繰り出す事が出来るのだ。事前動作が全くないから相手は攻撃を予測出来ず、当然よける事も避ける事も防御する事も不可能なのだ。
何が起きたのか理解する間もなく、もう一人の男子も次の瞬間には陽菜のパンチをもろに顔面にくらって同じように尻もちをつかされた。陽菜は両手で彼らのシャツの襟を一つずつつかんで床から引きずり起こして言った。
「いいか、よく聞け。今日限りこの学校では、福島モンいじめは一切なしだ」
「な、なんで、ですか?」
「やかましい。あたしがそう言ってんだから、黙って言う通りにしてりゃいいんだ。どうしても文句があるってんなら、人気のない校舎裏でゆっくり聞いてやる。その方がいいのか?」
陽菜の襟をつかまれたその二人の男子は、そろって首を何度も横に振った。
「ようし、じゃあ今日中に学校中に今の話、知らせて回れ。もし明日からこういう場面見つけたら、誰がやったかに関係なくてめえら二人に責任取らす。その意味、分かるな?」
穏やかな笑みを浮かべたまま言うから余計怖いようだ。男子二人は今度は機械仕掛けの人形のように必死で何度も首を縦に振った。
「ようし、じゃあ行け。いいな、今日中に触れまわっとけ!」
陽菜が手を話すと男子二人は鼻血まみれの顔面を押さえながら、全速力でその場から逃げて行った。いじめられていた姉の方が陽菜に「あの……」とこわごわ声をかけようとする。陽菜は掌をひらひらと振ってそれを遮った。
「ああ、いいよ。別に礼を言われるような事じゃない。ただな!」
そう言って陽菜は弟の方に詰め寄ってその胸ぐらをつかんで、相手の顔を引きよせた。
何が起きたのか理解する間もなく、もう一人の男子も次の瞬間には陽菜のパンチをもろに顔面にくらって同じように尻もちをつかされた。陽菜は両手で彼らのシャツの襟を一つずつつかんで床から引きずり起こして言った。
「いいか、よく聞け。今日限りこの学校では、福島モンいじめは一切なしだ」
「な、なんで、ですか?」
「やかましい。あたしがそう言ってんだから、黙って言う通りにしてりゃいいんだ。どうしても文句があるってんなら、人気のない校舎裏でゆっくり聞いてやる。その方がいいのか?」
陽菜の襟をつかまれたその二人の男子は、そろって首を何度も横に振った。
「ようし、じゃあ今日中に学校中に今の話、知らせて回れ。もし明日からこういう場面見つけたら、誰がやったかに関係なくてめえら二人に責任取らす。その意味、分かるな?」
穏やかな笑みを浮かべたまま言うから余計怖いようだ。男子二人は今度は機械仕掛けの人形のように必死で何度も首を縦に振った。
「ようし、じゃあ行け。いいな、今日中に触れまわっとけ!」
陽菜が手を話すと男子二人は鼻血まみれの顔面を押さえながら、全速力でその場から逃げて行った。いじめられていた姉の方が陽菜に「あの……」とこわごわ声をかけようとする。陽菜は掌をひらひらと振ってそれを遮った。
「ああ、いいよ。別に礼を言われるような事じゃない。ただな!」
そう言って陽菜は弟の方に詰め寄ってその胸ぐらをつかんで、相手の顔を引きよせた。