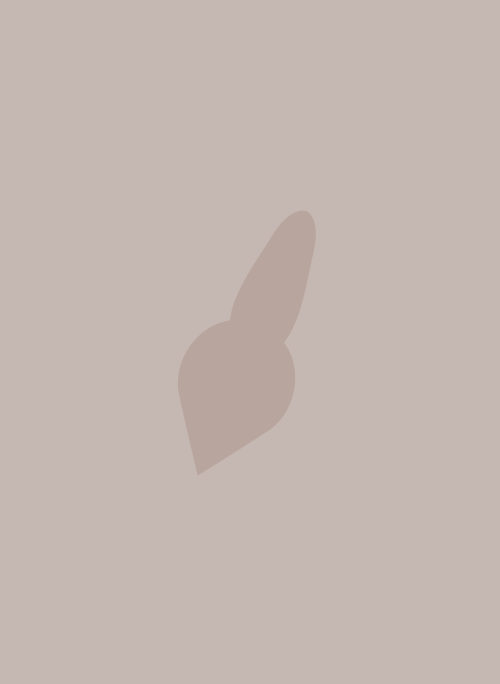立つことさえままならないこの足でどうやって逃げればいいのだろう。
ここまで来たのに……!!
危険を承知の上でそれでも覚悟してここまでやって来たというのに、ここまでなのかと悔しくて少女はまた唇を強く噛みしめた。
卑しく、おぞましい足音が徐々に大きくなってきている。
寒さと迫りくる死の恐怖で膝が、いや、膝だけでなくすべてがガクガクと小刻みに震えはじめていた。
真っ直ぐ松明を正面に掲げ、少女はそれでも懸命に前を見据えた。
挫けそうになる心をそれでも必死に奮い立たせ、絶対に諦めてなるものかと声にならない声でそう何度も呟いた。
松明の照らす光の手前でそれらはぴたりと立ち止まる。
何匹いるのか、少女には分からない。
けれど取り囲まれるほどには多くそこにいることは分かる。
死臭と言うべきか、醜悪な臭いが少女を取り囲むように漂い、シューシューという小さな穴から漏れ出る様な音がいくつもいくつも重なって聞こえてきていた。
光の端から黒いモノが一つ……二つ。
ゆっくりと姿を見せ始める。
少女はゴクリと唾を飲み込んだ。
松明を握るその手の中はびっしょりと濡れ、脇からも背中からも、そして額からも嫌な汗が垂れ落ちた。
ここまで来たのに……!!
危険を承知の上でそれでも覚悟してここまでやって来たというのに、ここまでなのかと悔しくて少女はまた唇を強く噛みしめた。
卑しく、おぞましい足音が徐々に大きくなってきている。
寒さと迫りくる死の恐怖で膝が、いや、膝だけでなくすべてがガクガクと小刻みに震えはじめていた。
真っ直ぐ松明を正面に掲げ、少女はそれでも懸命に前を見据えた。
挫けそうになる心をそれでも必死に奮い立たせ、絶対に諦めてなるものかと声にならない声でそう何度も呟いた。
松明の照らす光の手前でそれらはぴたりと立ち止まる。
何匹いるのか、少女には分からない。
けれど取り囲まれるほどには多くそこにいることは分かる。
死臭と言うべきか、醜悪な臭いが少女を取り囲むように漂い、シューシューという小さな穴から漏れ出る様な音がいくつもいくつも重なって聞こえてきていた。
光の端から黒いモノが一つ……二つ。
ゆっくりと姿を見せ始める。
少女はゴクリと唾を飲み込んだ。
松明を握るその手の中はびっしょりと濡れ、脇からも背中からも、そして額からも嫌な汗が垂れ落ちた。