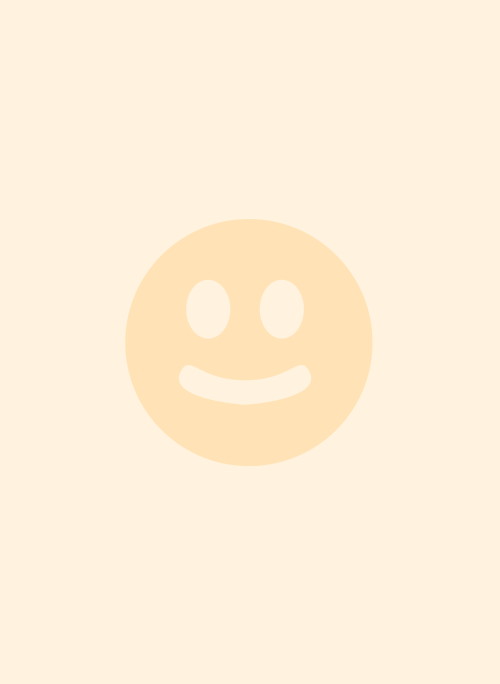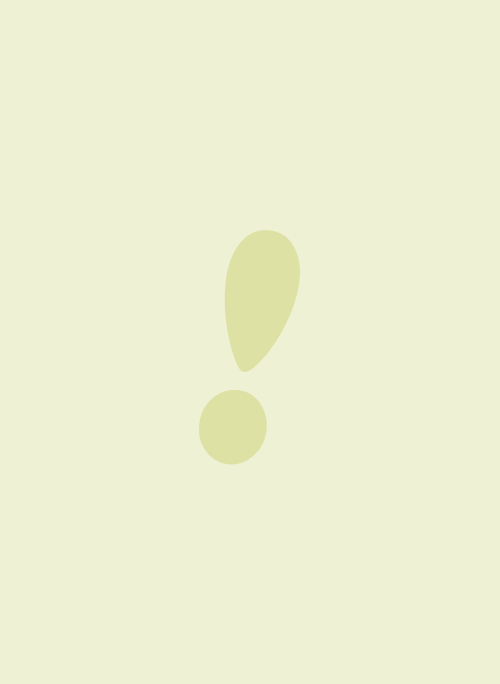僕は目を閉じて思い出していた。
『・・・麗、怖かったら、ここで死ぬのもありだし、逃げるのもありだ・・・。どうする?』
幼い僕にはよく理解できなかった。
ただ、うすい着物だけでは寒いはずなのに、佐助さんがいるだけで、すごく温かく感じた。
『僕は、逃げたりはしないし、死んだりもしません。一生、あなたについていきますよ・・・。だって僕は、あなたの右腕だから』
『ふっ、いい子だ・・・。そういうところが好きだ』
笑ってくれる佐助さんはかっこよくて、憧れだったんだ・・・。
『・・・麗、怖かったら、ここで死ぬのもありだし、逃げるのもありだ・・・。どうする?』
幼い僕にはよく理解できなかった。
ただ、うすい着物だけでは寒いはずなのに、佐助さんがいるだけで、すごく温かく感じた。
『僕は、逃げたりはしないし、死んだりもしません。一生、あなたについていきますよ・・・。だって僕は、あなたの右腕だから』
『ふっ、いい子だ・・・。そういうところが好きだ』
笑ってくれる佐助さんはかっこよくて、憧れだったんだ・・・。