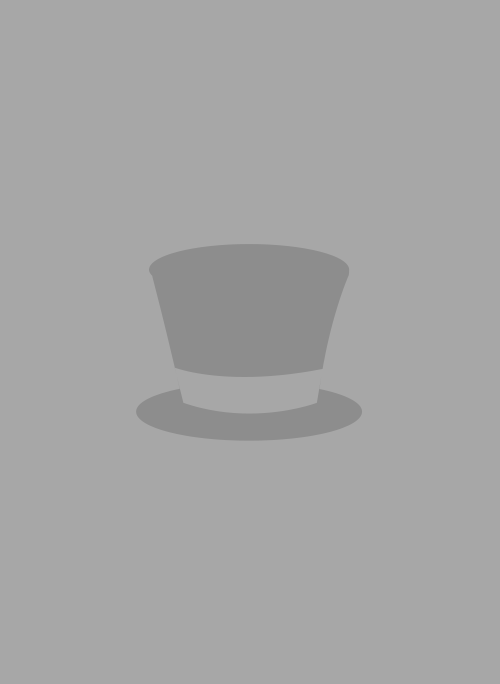部屋の中にアッサムのいい香りが漂う事に気づき、夢から覚めた。
9月下旬ということもあり、夏の余韻を残しているのは昼間くらいで朝はかなり肌寒い。
布団から出るのが億劫な私にとっては、最高の目覚ましと言っても過言ではないだろう。
「お嬢様。紅茶が入りましたよ。」
低く甘い声が耳に入ってくる。
わざと聞こえないフリをして布団をもう一度かぶり直した。
「早く起きていただかないと、せっかく入れた紅茶が冷めてしまいますよ。」
「…」
「起きないというなら仕方ない。強引に起こしましょう。まずお湯を頭から…」
「…わかった!起きればいいんでしょ!このクソ執事!」
根負けした私は文句をいいながら体を乱暴に起こす。
こいつは冗談ではなく本当にやりかねないのだ。