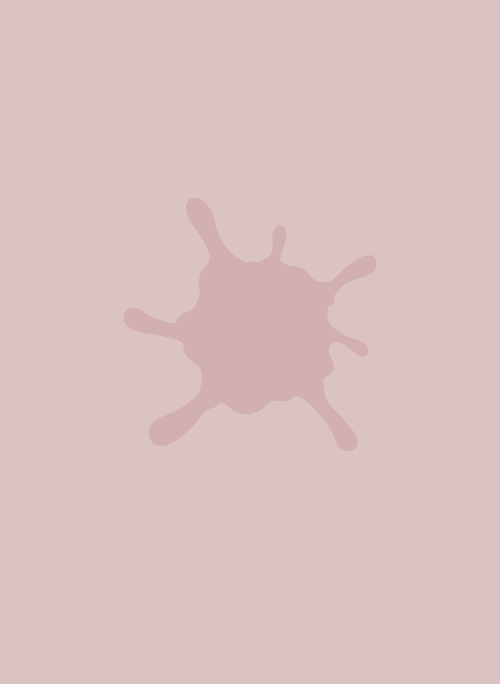病院の側の喫茶店に三人は来ていた。
「どう?一緒に暮らさない?」
医者の話を踏まえて、美優は姉に訊いた。
「でも・・・。」
美優も、幸男も自分を知っているかもしれない。それに写真を見る限り、家族なのだろう。それはわかる。しかし、記憶がないと言うのは、家族を他人にさせる。見ず知らずの他人と一緒に暮らせるだろうか。無理だ。
「ねぇ、一緒に暮らそうよ。」
幸男も必死だ。しかし、その幸男の必死さは、美喜を苦しめるだけだった。
「ごめんね。僕の気持ちはわかるよ。でも、でもね、本当に覚えてないの。だから、こう言ってはあれだけど、二人とも知らない人に見えるの。ごめんね。だから、一緒に暮らすのは・・・。」
幸男が泣き出したのは言うまでもない。
「泣かないで。泣かないで、ね、お願い。」
しかし、泣きやむわけもない。
「姉さん、今のは言い過ぎだよ。」
「そんな事言われても・・・。」
美喜は混乱した。今の美喜にとっては、あくまでも他人なのだ。“お母さん”だとか“姉さん”だとか言われてもどうする事も出来ない。しばらく悩んだ。
「わかった。じゃ、こうしましょ。」
何か含みを持たせた言い方だ。
「何?」
幸男は両方の穴から鼻水を垂らしながら、美喜の方を見た。あまりの鼻水に、テーブルの上にあったナプキンを取り、美喜はその鼻水を拭いた。
「毎日、晩ご飯を一緒に食べるって言うのはどうかな?私もこの近所に住んでいるわけだし、それくらいなら構わないよ。」
幸男は考えた。鼻水を拭かれた鼻は、真っ赤になっている。そのせいか、少し痒かった。その鼻を掻きながら言った。
「わかった。それでいいよ・・・。」
納得はしていなかった。その証拠に顔はふて腐ったままだ。でも、そう言うしかなかった。ここで嫌だと言ったら、母親がまたいなくなってしまう気がしたからだ。
「ありがとう。わかってくれて。」
美喜は笑った。
幸男と美優は目を見合わせた。
「どう?一緒に暮らさない?」
医者の話を踏まえて、美優は姉に訊いた。
「でも・・・。」
美優も、幸男も自分を知っているかもしれない。それに写真を見る限り、家族なのだろう。それはわかる。しかし、記憶がないと言うのは、家族を他人にさせる。見ず知らずの他人と一緒に暮らせるだろうか。無理だ。
「ねぇ、一緒に暮らそうよ。」
幸男も必死だ。しかし、その幸男の必死さは、美喜を苦しめるだけだった。
「ごめんね。僕の気持ちはわかるよ。でも、でもね、本当に覚えてないの。だから、こう言ってはあれだけど、二人とも知らない人に見えるの。ごめんね。だから、一緒に暮らすのは・・・。」
幸男が泣き出したのは言うまでもない。
「泣かないで。泣かないで、ね、お願い。」
しかし、泣きやむわけもない。
「姉さん、今のは言い過ぎだよ。」
「そんな事言われても・・・。」
美喜は混乱した。今の美喜にとっては、あくまでも他人なのだ。“お母さん”だとか“姉さん”だとか言われてもどうする事も出来ない。しばらく悩んだ。
「わかった。じゃ、こうしましょ。」
何か含みを持たせた言い方だ。
「何?」
幸男は両方の穴から鼻水を垂らしながら、美喜の方を見た。あまりの鼻水に、テーブルの上にあったナプキンを取り、美喜はその鼻水を拭いた。
「毎日、晩ご飯を一緒に食べるって言うのはどうかな?私もこの近所に住んでいるわけだし、それくらいなら構わないよ。」
幸男は考えた。鼻水を拭かれた鼻は、真っ赤になっている。そのせいか、少し痒かった。その鼻を掻きながら言った。
「わかった。それでいいよ・・・。」
納得はしていなかった。その証拠に顔はふて腐ったままだ。でも、そう言うしかなかった。ここで嫌だと言ったら、母親がまたいなくなってしまう気がしたからだ。
「ありがとう。わかってくれて。」
美喜は笑った。
幸男と美優は目を見合わせた。