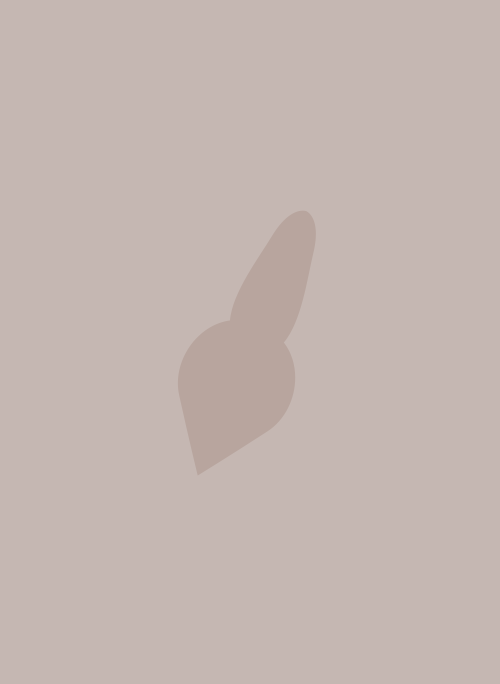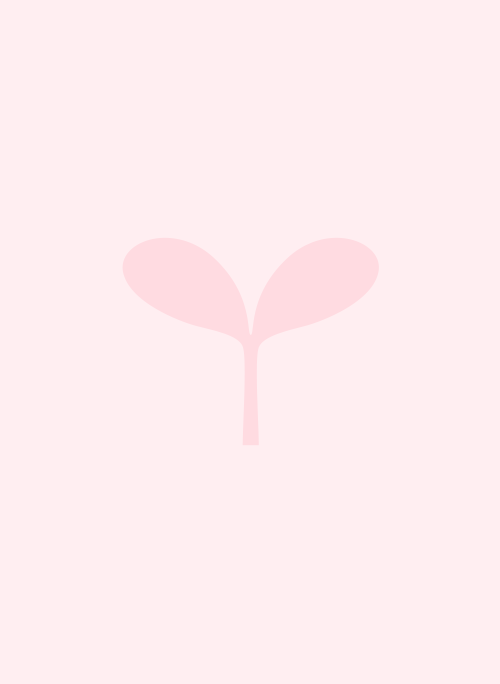警備員がドスのきいた太い声を張り上げた。
近づいてきた警備員は僕達から数メートル離れた場所で動きを止めた。
僕らを警戒しているらしい。
「アンドロイドか?何をしている!すみやかに登録名と理由を答えろ!」
警備員は、からみ合ったままの僕とA7を一体のアンドロイドと思い込んだらしい。
チャンスは今しかない。
A7のメインスイッチを切って僕だけ名乗れば、全部ひとりでしたことになる。
僕はA7の背中に回った腕を、必死に動かしA7の首元にあるメインスイッチに手を伸ばそうとした。
しかしA7のしめつける力が尋常な強さでないことと、忘れていた恐怖心が一気によみがえり、なかなか思うように体が動かない。
近づいてきた警備員は僕達から数メートル離れた場所で動きを止めた。
僕らを警戒しているらしい。
「アンドロイドか?何をしている!すみやかに登録名と理由を答えろ!」
警備員は、からみ合ったままの僕とA7を一体のアンドロイドと思い込んだらしい。
チャンスは今しかない。
A7のメインスイッチを切って僕だけ名乗れば、全部ひとりでしたことになる。
僕はA7の背中に回った腕を、必死に動かしA7の首元にあるメインスイッチに手を伸ばそうとした。
しかしA7のしめつける力が尋常な強さでないことと、忘れていた恐怖心が一気によみがえり、なかなか思うように体が動かない。