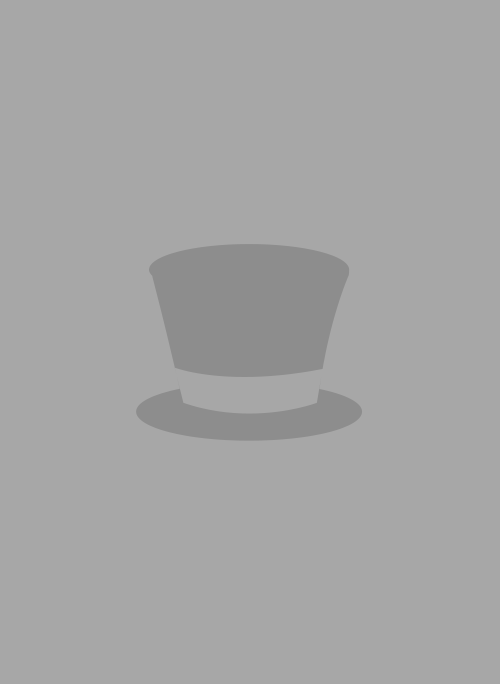「痛っ…。」
小さい声で、
そう言っているのが聞こえた。
これ以上
コイツが痛めつけられるのは、
もう見たくない。
やってはいけない
行動だというのは
充分に分かっている。
だけど、無理だ。
我慢なんて
できるはずがない。
ガラスの破片が
足にささるのなんて気にせずに、
座り込んでいる俊稀の横に
俺は駆け寄った。
「ちょっ…!
来るなって!
来ちゃったら…‼」
小さい声で、
そう言っているのが聞こえた。
これ以上
コイツが痛めつけられるのは、
もう見たくない。
やってはいけない
行動だというのは
充分に分かっている。
だけど、無理だ。
我慢なんて
できるはずがない。
ガラスの破片が
足にささるのなんて気にせずに、
座り込んでいる俊稀の横に
俺は駆け寄った。
「ちょっ…!
来るなって!
来ちゃったら…‼」