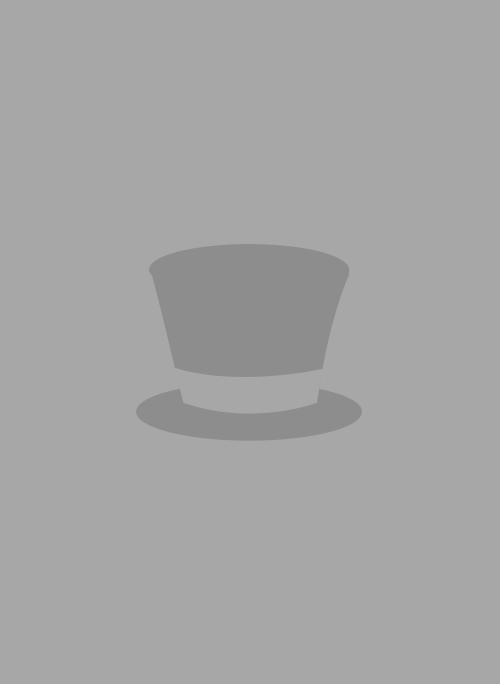俺はもう半狂乱になっていたのだろう。時々母ちゃんと美紅の声が聞こえてはいたが、それは俺の耳には入らなかった。俺は二人がかりでソファに押さえつけられながら天井に向かってわめき散らしていた。
まるで自分の声じゃないみたいだった。自分でもよく覚えてはいないが、多分こんな内容の事を口にしていたのだろうと思う。
「違う!あいつは、純は、いじられキャラってやつで。だからいじめた覚えなんてないんだ!だから、そうじゃなくて、ただ、ふざけてただけで。そりゃあいつらは時々手を出したりはしてたけど、でも、それだって暴力ってほどじゃなかったし。あれも、あれも、あれも、あれも、みんな遊びだったんだ!ふざけてただけなんだ!いじめとか、そんなんじゃ……だから、そんな……頼むから信じてくれよ!」
俺の耳に「いいから落ち着きなさい」とか「ニーニ、しっかりして」とか、声が聞こえていたが、それはまるで遠い別の世界から響いてくる音のようにしか聞こえなかった。俺はもう叫ぶように繰り返した。
「だから違うんだって!いじめなんかじゃなかった!そんなつもりはなかったんだよ!俺にはそんなつもりは……だから、だから、だからああああああああ!」
次の瞬間、バシーンと鋭い音が部屋中に響いた。それで俺はハッと我に帰った。途端に左の頬が熱くなってヒリヒリ痛んだ。あれは母ちゃんが俺の頬を思いっきり引っ叩いた音だったんだと、やっと気がついた。
俺の両肩を母ちゃんが両手で前からソファに押しつけていた。ソファの後ろから美紅が俺の胸に両手を回してやはりソファに押さえつけている。二人とも汗まみれだった。どうやら俺はすいぶん興奮して暴れていたようだ。
呆けている俺の顔に自分の顔をぐっと近づけながら母ちゃんが言う。
「ええ、信じるわよ、あたしも美紅もね。それにあんたが直接手を出してなかった事はクラスの他の子が何人も証言してくれたわ。だから、あんた自身はあの時学校にも警察にも呼ばれなかったでしょ?」
まるで自分の声じゃないみたいだった。自分でもよく覚えてはいないが、多分こんな内容の事を口にしていたのだろうと思う。
「違う!あいつは、純は、いじられキャラってやつで。だからいじめた覚えなんてないんだ!だから、そうじゃなくて、ただ、ふざけてただけで。そりゃあいつらは時々手を出したりはしてたけど、でも、それだって暴力ってほどじゃなかったし。あれも、あれも、あれも、あれも、みんな遊びだったんだ!ふざけてただけなんだ!いじめとか、そんなんじゃ……だから、そんな……頼むから信じてくれよ!」
俺の耳に「いいから落ち着きなさい」とか「ニーニ、しっかりして」とか、声が聞こえていたが、それはまるで遠い別の世界から響いてくる音のようにしか聞こえなかった。俺はもう叫ぶように繰り返した。
「だから違うんだって!いじめなんかじゃなかった!そんなつもりはなかったんだよ!俺にはそんなつもりは……だから、だから、だからああああああああ!」
次の瞬間、バシーンと鋭い音が部屋中に響いた。それで俺はハッと我に帰った。途端に左の頬が熱くなってヒリヒリ痛んだ。あれは母ちゃんが俺の頬を思いっきり引っ叩いた音だったんだと、やっと気がついた。
俺の両肩を母ちゃんが両手で前からソファに押しつけていた。ソファの後ろから美紅が俺の胸に両手を回してやはりソファに押さえつけている。二人とも汗まみれだった。どうやら俺はすいぶん興奮して暴れていたようだ。
呆けている俺の顔に自分の顔をぐっと近づけながら母ちゃんが言う。
「ええ、信じるわよ、あたしも美紅もね。それにあんたが直接手を出してなかった事はクラスの他の子が何人も証言してくれたわ。だから、あんた自身はあの時学校にも警察にも呼ばれなかったでしょ?」