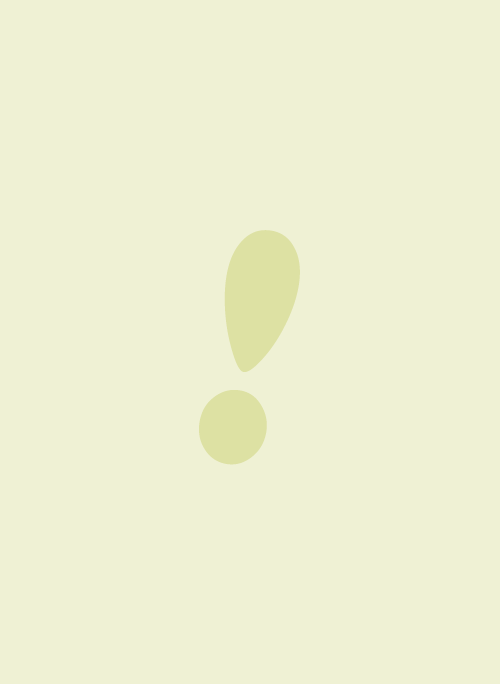「………だけど、あなたとは、もう…あえないから…」
『ボク、君のタメならいくらでも出せるよお?!たとえ、借金したって…』
援助の相手はなきじゃくりながら言う。
あたしは言葉を遮って言った。
「あたしのためにお金つかわないで…あなたにそんな風になってほしく、ないの」
ぎゅっと目をつむり、くちびるを噛み締めた。
このひとはあたしに出逢ったことで、全てが変わってしまった。
『ボクをこんなふうにさせたのは君じゃないか!』
援助の相手は怒り、泣きながら言う。
「……わかってる…ごめんなさい…」
『責任とれよ!』
「それは出来ない」
『なんだよ、ボクをこんなふうにしておいて…』
そんなやり取りが小一時間は続いただろう。
ごめんなさい、としか言わなくなったあたしに相手は泣く泣く電話を切ってくれた。
「………ふー…」
あたしがベッドに腰かけると、
「おつかれ。これ」
俊輔はあったかいカフェオレをいれてくれた。
「…わあ…おいしそう…いただきます」
あたしはカフェオレのんで疲れたからだを癒した。
「大変そうだったな。誰だったんだよ?」
苦笑いしながら聞いてきた俊輔。
「ん、昔してた援助の相手」
「………は?」
「あれ?はなしてなかったっけ」
あたしはホットカフェオレを両手で包みながら言った。
「援助してたのかよ?」
「うん」
「………もっと自分大事にしろよ…」
そう言ってあたしを引き寄せた。
「……あ…」
あたしの手からカフェオレのカップが落ちて、中身がこぼれる。
「俊輔、カフェオレこぼれちゃっ…」
あたしの顔にぱたっと液体がおちたかと思うとそのまま抱き締められた。
「………俊輔…?」
俊輔は返事することなく、あたしを抱きしめつづけた。