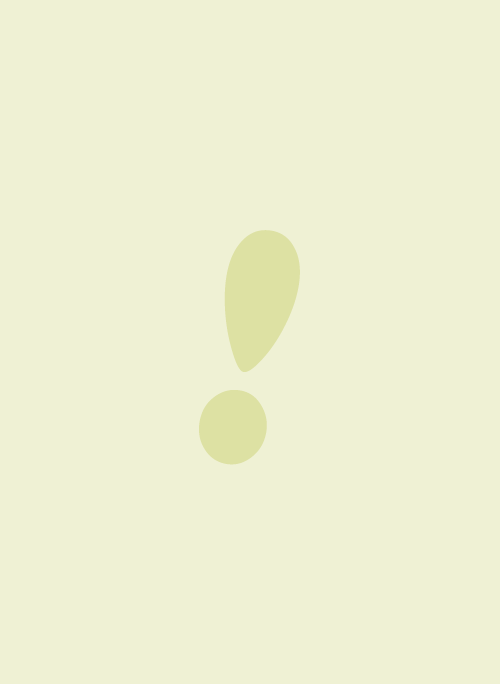そして進みはじめたベンツ。
「…嫌…嫌…!」
あたしは肩を震わせ、ドアを開けようと試みるが…開かない。
「…嫌、やめて…はなしてだして!」
あたしは気が狂ったように窓を叩く。
厳重にロックされた窓はビクともしない。
「…嫌ぁっ…!」
見てみぬフリをする、運転手。
笑顔で手をふる、家政婦。
全てが嫌だった。
嫌なの。あいたくないの。
あのふたりだけは。
仮面を被ったふたりの顔。
狂気に満ちる、あの笑顔。
何かを隠す、あの態度。
全てが、偽りで。
本当の顔は、見えない。
遠い遠い昔に。
何か大切なものを奪われた。
とてつもない恐怖を植え付けられた。
そんな気がするのだ。
絶対にあのふたりだけは信用できない――
~♪
悶々と嫌な記憶と闘っていると、携帯が鳴った。
メールボックスを開くと、見慣れた名前。