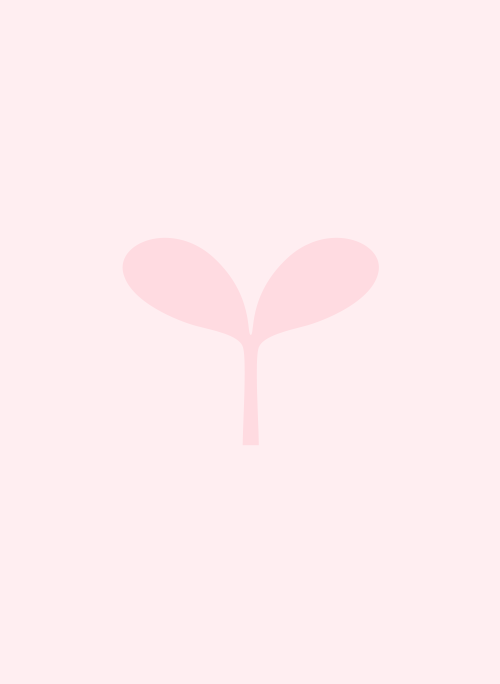わたし、やっぱりだめかも。
しのがいう。
今にも泣きそうな声で。
俺はしのを不安にさせた。
今まで居心地のよかった幼なじみの関係を、俺は自分で粉々にぶち壊した。
「し、の、」
やっと出た声はかすれていて、でもしのには届いていたようで。
「私、れいくんの彼女にはなれなかったね」
ばいばいと手を振って、しのは公園から出て行った。
追いかければ、まだ間に合ったかもしれないのに、俺の足は、膝は、立ち上がれなくなっていた。
無惨にも、どんどん離れて小さくなるしのを、無様に見送るしかなかった。
なんて、
窮屈なんだ。