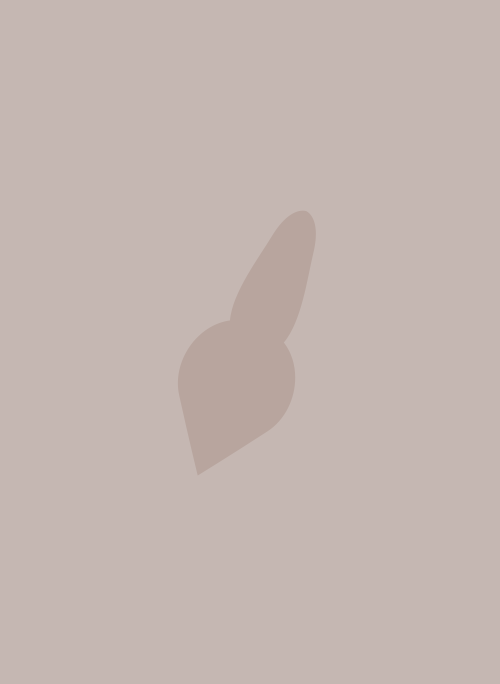翌朝。
レイシアとシギは少ない荷物をまとめ、まだ暗いうちに宿を出た。
トクルーナから王都までは、徒歩では丸一日ほどかかる。
途中で野宿するほどの距離でもないので、王都の城門が閉められる日暮れまでにはたどり着きたかった。
村の外までルシールとルウは2人を見送ってくれた。
ルウはわんわんと泣いたが、ルシールは泣かなかった。
「お世話になりました。」
レイシアのその言葉にルシールはにっこりと微笑む。
「こちらこそいろいろ手伝っていただいて。
ありがとうございます。」
それからルシールはルウの頭をなで、なだめるように言う。
「ほら、ルウ。
ちゃんとあいさつしないと、後で後悔しちゃうわよ。」
それにルウが泣きながらうなずき、
「レイシアありがとう。
シギさんもありがとう。
2人とも気をつけてね。」
と言う。
レイシアはしゃがんでルウの顔をのぞきこみ、
「どういたしまして。
ルウさんもお元気で。」
と言う。
シギもぽんとルウの頭をなでると、ルシールを見つめる。
ルシールの目は多少腫れてはいるが、涙を流す気配はなかった。
それにシギは安心して微笑む。
ルシールもそれに微笑み返す。
「じゃあ、行きますよ。」
レイシアはそう言ってコートのフードを目深にかぶり、踵を返す。
シギも、はい、と返事をして踵を返そうとするが、一度立ち止まりルシールを見る。
ルシールは自分がかけていたエプロンを外しルウの頭にかぶせると、シギに駆け寄る。
シギは駆け寄るルシールの手をとり、2人は一度だけキスをした。
一瞬でルシールは離れ、
「待ってます。」
と言って微笑む。
それにシギはルシールの頭をなで、フードをかぶり踵を返した。
ルシールはレイシアのあとを追うシギの背中を見送る。
そこでかぶされたエプロンから顔を出したルウが、
「なに?なんでエプロン…」
と言うが、それには答えず、ルシールは遠くなっていく背中をいつまでも見送っていた。