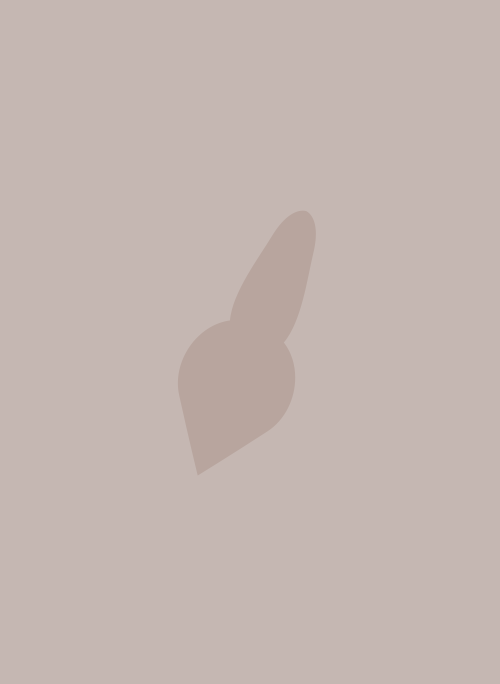淡々とそう言うシギに、ダグラスとレイシアは一瞬黙り込んだあと、声を上げて笑った。
小さく笑いながら、レイシアは指をぱちんと鳴らす。
途端。
「なんなの?!!
女の子を木に縛り付けといてほっとくってどういうこと?!
ていうか何をこそこそしてんのよ!!
聞こえないんですけどー!」
甲高い声が聞こえはじめ、3人同時に顔をしかめる。
レイシアはナイフの先についた湯気のたつ干し肉をとり、口にくわえる。
そして立ち上がり、虫をはらうかのように軽く右手を振る。
「きゃあっ!!」
その途端なぜか背後で上がった聞き慣れた悲鳴にダグラスとシギが振り向くと、さっきレイシアが放り投げたナイフがまた少女の顔すれすれのところに刺さって揺れていて。
「では、遠慮なく。」
干し肉を手に持ったレイシアが、にっこりと微笑んだ。
「う………だ、だから、その……」
「はい?よく聞こえません。」
「ま、まだなんにも言ってな……って、ごめんなさいごめんなさい!!
もう嫌…………」
「もう一度聞きますよ。
あなたの出身は?」
「えっ…と……あの、あたしシーフだから、故郷とかそういうのは………」
「………。」
「うそ!うそうそうそ!ある!あります!だからナイフ離してよ!こわい!!こわいから!!」
幾度となく上がる悲鳴に、もうダグラスとシギは慣れたように耳を貸さなかった。
シギにいたっては、たき火に当たりながら座った状態で、うとうとと目を閉じたり開いたりしていて。
まだ木に縛り付けられたままの少女のまわりには、数本のナイフが少女すれすれの位置に刺さり、さらに他にもナイフが刺さったあとが所々に残っていた。
その目の前にしゃがみ込んだレイシアは、いつもの微笑みを消した無表情で、少女の眼球に当たるか当たらないかのところに見事にナイフを突き付けている。