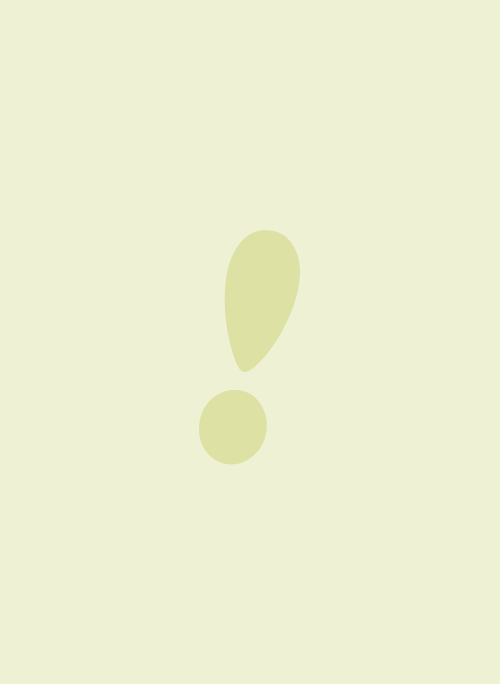「あみね、この下にいるの」
「うん」
いつの間にか、体の自由が利くようになっていた。私はあみちゃんに振り返る。
そこには、小さな肩を震わせながら啜り泣きする一人の少女がいた。
「一人は淋しいよ…」
「そうだね」
「一人はいやだよ…」
「そうだね」
私はあみちゃんをそっと抱きしめた。幽霊でも、この子の悲しみは、確かに伝わってきた。
「おねえちゃん…」
「………」
迷子の子が、母親を探すような目で私に言う。
「一緒に来てよぉ…」
始めから殺す気だったんだね…。いや、確かにそうだけど、この子は、一人がいやなだけ、だから一緒にいてくれる人が欲しかったんだ…。
私は…。
「私は…」
「本当に連れていきたいのか?」