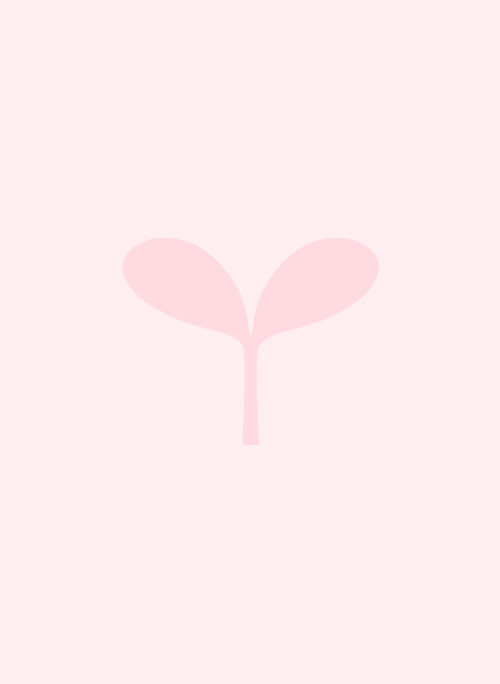*
朝靄の立ち込める中庭に、そっと寄り添う二つの影があった。
鳥の啼く声すら、聞こえない静寂に包まれながら、また二人も無言だった。
滑らかなダークブラウンの髪を梳いてやりながら、男は腕の中の女を見つめた。
寂しそうに震える目には、涙が溜まっている。
眉を微かに震わせながら、彼は彼女を見つめ続ける。
どれくらいそうしていたか、彼女は鈴のなるような声で、ゆっくりと言った。
「愛しています。」
それは、初めて聞く言葉だった。
彼は濡れた眼を、大きく見開く。
彼女は驚く彼に微笑んで、そっと頬に手をあてた。
優しく頬を撫でながら、もう一度小さな声で、しかしはっきりと言った。
「私は、貴方を愛しています、ジーク。」
彼__ジークは胸が詰まって言葉にならなかった。
浅い呼吸を繰り返すジークに、彼女はさらに言った。
「誰がなんと言おうと、私が貴方を愛することは変わらない、変えさせない。
心の底から貴方が愛しい。
だから、それだからこそ、貴方に幸せになってもらいたいの。」
「ミア…。」
「最初からこうなることはわかっていたはずでしょう?
人生で一番幸せな時間を作ることができたのだから、もうこれ以上は望んではいけないのよ。
これからはお互い歩むべき道を、進みましょう。」
ぐっと息を飲んでから、ジークは微笑んだ。
「あぁ。」
彼女の手が、彼から離れた。
:
:
・
・
・
・