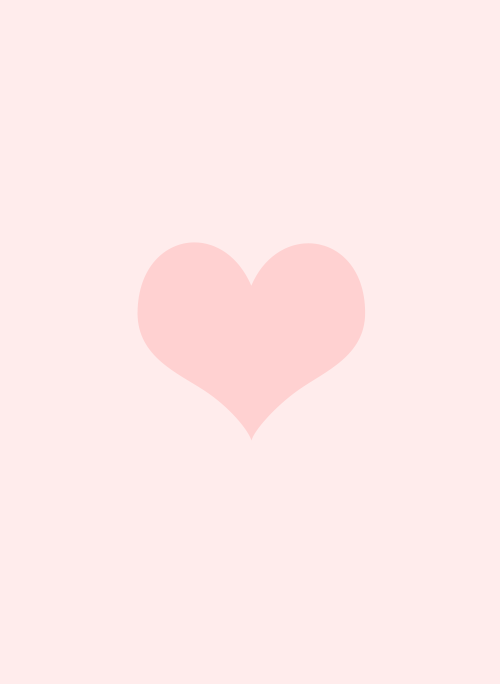昼近くまで六人は、丘の芝生でバドミントンや相撲に興じていた。
やがて、そんなみんなの楽しむ姿を笑顔で見ていた奈央が、丘の下の道路に屋台が立ち並び始めたのを見つけて、思わず叫んだ。
「あ、屋台だ!」
そう言うと、奈央は裕美のほうを見た。
「ねえ、行ってみようよ。香澄も行こう。」
「いいね。ねえ、裕美。行こうよ。」
香澄の声にも後押しされて、裕美はうれしそうに頷いた。そして、三人は丘を降り始める。
あわてて尾上が声をかけた。
「おい、俺らを置いていくのかよ。」
「じゃあ、尾上君。ボディーガードとしてついて来てくれる?」
香澄が振り返ってそう言うと、尾上は苦笑して閉口した。
その横で土門が大笑いをして、その背中を何度か叩いた。
尾上は少し膨れっ面で下っていく女性三人の後ろ姿を見ていたが、やがて小さく頷くとそのあとに続いて丘を駆け下りていった。
そんな四人の姿が見えなくなると、土門はバドミントンセットを片付けているケンジに近づいた。
「ケンジ。ちょっといいか。」
土門はケンジにそう声をかけると、数メートル離れた海の見える位置に腰を下ろした。
その様子に、ケンジは少し戸惑ったが、バドミントンセットを抱えたまま、土門の横に座った。
「どうした。」
ケンジはそう声をかけたが、土門は海のほうを向いたまま何も言葉を発しない。
そんな親友の様子を見て、ケンジは小さく息を吐いて、倣うように海を見つめた。
そしてどのくらいがたったであろうか。
土門はぽつりと言った。
「なあ、ケンジ。裕美に、きちんと別れを告げられるんだろうな。」
ケンジは、思わず右に座る土門の顔を見た。
「そりゃあ、まあ…。」
ケンジの歯切れの悪い返答に、土門は多少いらついたような口調で言った。
やがて、そんなみんなの楽しむ姿を笑顔で見ていた奈央が、丘の下の道路に屋台が立ち並び始めたのを見つけて、思わず叫んだ。
「あ、屋台だ!」
そう言うと、奈央は裕美のほうを見た。
「ねえ、行ってみようよ。香澄も行こう。」
「いいね。ねえ、裕美。行こうよ。」
香澄の声にも後押しされて、裕美はうれしそうに頷いた。そして、三人は丘を降り始める。
あわてて尾上が声をかけた。
「おい、俺らを置いていくのかよ。」
「じゃあ、尾上君。ボディーガードとしてついて来てくれる?」
香澄が振り返ってそう言うと、尾上は苦笑して閉口した。
その横で土門が大笑いをして、その背中を何度か叩いた。
尾上は少し膨れっ面で下っていく女性三人の後ろ姿を見ていたが、やがて小さく頷くとそのあとに続いて丘を駆け下りていった。
そんな四人の姿が見えなくなると、土門はバドミントンセットを片付けているケンジに近づいた。
「ケンジ。ちょっといいか。」
土門はケンジにそう声をかけると、数メートル離れた海の見える位置に腰を下ろした。
その様子に、ケンジは少し戸惑ったが、バドミントンセットを抱えたまま、土門の横に座った。
「どうした。」
ケンジはそう声をかけたが、土門は海のほうを向いたまま何も言葉を発しない。
そんな親友の様子を見て、ケンジは小さく息を吐いて、倣うように海を見つめた。
そしてどのくらいがたったであろうか。
土門はぽつりと言った。
「なあ、ケンジ。裕美に、きちんと別れを告げられるんだろうな。」
ケンジは、思わず右に座る土門の顔を見た。
「そりゃあ、まあ…。」
ケンジの歯切れの悪い返答に、土門は多少いらついたような口調で言った。