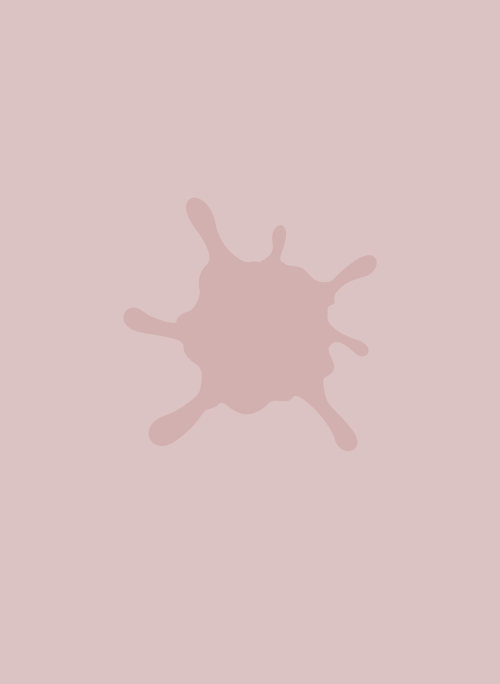その日は外で食事を取りながら、これまでのさまざまな経緯を聞かれた。こんな話が記事になるのかどうか、という疑問はあったが、相沢は
「貴重な話ですよ。女性のネットカフェ難民は少ないですからね」
と言いながら、嬉しげにノートにペンを走らせている。
自分がたどってきたこの二年間。話しながら、私は心が軽くなってゆくのを感じていた。
誰にも話せない苦悩。
私はずっと誰かに話したかったのだろうか。誰かに聞いてもらいたかったのだろうか。
悲しい過去を話すうちに、私の瞳は涙であふれていた。
色んなことがあった。どれも一口には言えない事件ばかりだ。ささいな事でも、心に深いダメージを負う事件もある。
胸の奥深くに隠していた感情が、話すことによって解放されたかのようだった。
そんな私を見て、相沢はハンカチを差し出してくれた。
「すいません、こんなとこ……他の人が見たら別れ話してるみたいに思われますね」
涙を拭きながら、そんな冗談を言える余裕が出てくると、この話が記事になれば
(もしかしたら色んなところから、救いの手がさし伸ばされるかも知れない)
という、淡い期待すら抱いてしまっていた。
私はすっかり信じ込んでいた。この男がフリーライターだということに。
ホテルは平凡なビジネスホテルだった。
相沢は鍵を受け取ると、私を部屋へ案内した。
「あの……」
しかし見たところ、鍵をひとつしか受け取っていない。それは
(まさか、同じ部屋じゃ)
ということではないだろうか。
「貴重な話ですよ。女性のネットカフェ難民は少ないですからね」
と言いながら、嬉しげにノートにペンを走らせている。
自分がたどってきたこの二年間。話しながら、私は心が軽くなってゆくのを感じていた。
誰にも話せない苦悩。
私はずっと誰かに話したかったのだろうか。誰かに聞いてもらいたかったのだろうか。
悲しい過去を話すうちに、私の瞳は涙であふれていた。
色んなことがあった。どれも一口には言えない事件ばかりだ。ささいな事でも、心に深いダメージを負う事件もある。
胸の奥深くに隠していた感情が、話すことによって解放されたかのようだった。
そんな私を見て、相沢はハンカチを差し出してくれた。
「すいません、こんなとこ……他の人が見たら別れ話してるみたいに思われますね」
涙を拭きながら、そんな冗談を言える余裕が出てくると、この話が記事になれば
(もしかしたら色んなところから、救いの手がさし伸ばされるかも知れない)
という、淡い期待すら抱いてしまっていた。
私はすっかり信じ込んでいた。この男がフリーライターだということに。
ホテルは平凡なビジネスホテルだった。
相沢は鍵を受け取ると、私を部屋へ案内した。
「あの……」
しかし見たところ、鍵をひとつしか受け取っていない。それは
(まさか、同じ部屋じゃ)
ということではないだろうか。