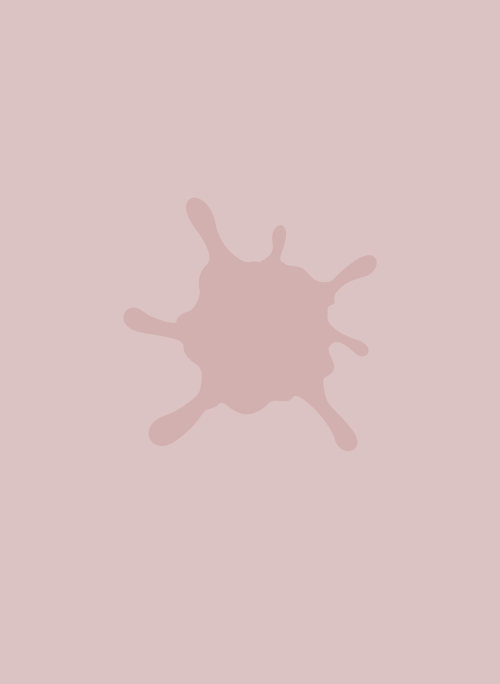「……ん……まあ、そんな感じ。バカでしょ、私」
なんだか鼻がむず痒い。鼻をひとすすりすると、思わぬ大きな音が出た。
「ダメ人間って言われて……ホント、こんなんじゃダメだ」
視界に映る夏子さんの顔が滲んだのを見とめて、私はいつの間にか涙があふれていることに気づいた。
「お腹蹴られて、言うこと聞かないと子供を殺すって……だから私」
「雪……」
あの夜はさめざめと泣いた。そして朝が来ると、自分の中で決着をつけたのだ。
(私にこれ以上堕ちる場所はない。だから前だけを向いていこう)
……と。
それなのに、胸の奥にしまっていたはずの感情が次から次へと噴き出してくる。
悔しさと悲しみと怒り。
何もかもあの夜のままだ。私は何も吹っ切れていなかった。ただ、無理やりしまいこんでいただけだったのだ。
「お金が無いって……悪いことなんですか?」
夏子さんは、無き濡れた私を包みこんでくれる。そして頭をなでてくれた。
それはずいぶんと昔のことだ。母が泣き止まない私をあやしてくれた温かさに、どこか似ていて、さらに涙があふれた。
「そんなことないよ。雪は一生懸命生きてるじゃない。胸を張れるよ」
「だって……みんな私を見下して……いじわるばかりで……助けてくれる人は居なくなっちゃうし」
「大丈夫。今は私がいるじゃない」
「私、生きてていいのかな……ホントにダメ人間じゃないのかな」
泣きじゃくる私を、夏子さんの腕が力強く抱きしめた。
「当たり前じゃない。真面目に生きてきたからこんな生活してるんでしょ」
そう言って頭をまた撫でてくれた。
私は何度もうなずきながら、その手の温もりに母を重ね合わせてまた泣いた。
なんだか鼻がむず痒い。鼻をひとすすりすると、思わぬ大きな音が出た。
「ダメ人間って言われて……ホント、こんなんじゃダメだ」
視界に映る夏子さんの顔が滲んだのを見とめて、私はいつの間にか涙があふれていることに気づいた。
「お腹蹴られて、言うこと聞かないと子供を殺すって……だから私」
「雪……」
あの夜はさめざめと泣いた。そして朝が来ると、自分の中で決着をつけたのだ。
(私にこれ以上堕ちる場所はない。だから前だけを向いていこう)
……と。
それなのに、胸の奥にしまっていたはずの感情が次から次へと噴き出してくる。
悔しさと悲しみと怒り。
何もかもあの夜のままだ。私は何も吹っ切れていなかった。ただ、無理やりしまいこんでいただけだったのだ。
「お金が無いって……悪いことなんですか?」
夏子さんは、無き濡れた私を包みこんでくれる。そして頭をなでてくれた。
それはずいぶんと昔のことだ。母が泣き止まない私をあやしてくれた温かさに、どこか似ていて、さらに涙があふれた。
「そんなことないよ。雪は一生懸命生きてるじゃない。胸を張れるよ」
「だって……みんな私を見下して……いじわるばかりで……助けてくれる人は居なくなっちゃうし」
「大丈夫。今は私がいるじゃない」
「私、生きてていいのかな……ホントにダメ人間じゃないのかな」
泣きじゃくる私を、夏子さんの腕が力強く抱きしめた。
「当たり前じゃない。真面目に生きてきたからこんな生活してるんでしょ」
そう言って頭をまた撫でてくれた。
私は何度もうなずきながら、その手の温もりに母を重ね合わせてまた泣いた。