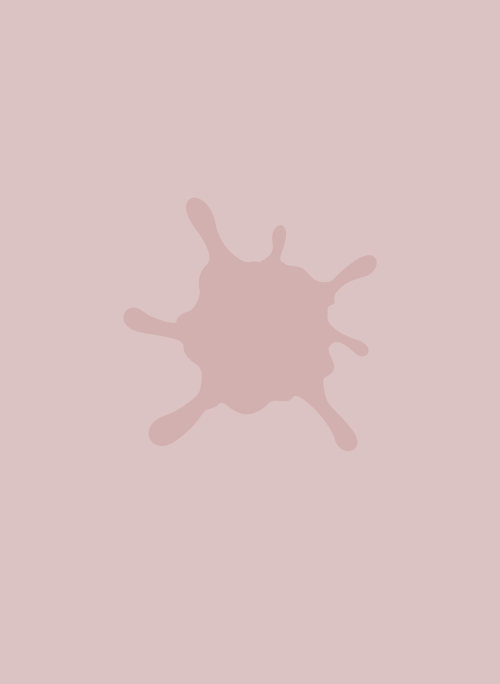「借金、どうなった?」
「なんでそんなこと聞くの?」
「そりゃ心配してたからだよ」
電話もメールの一通もなしで、心配してたなどとよく言えたものだ。
「仕事……なにしてるんだ。もしかして、今から出勤か?」
この近くには夜の歓楽街もある。一郎の考えていることが分かると、その浅はかな想像にため息がもれた。
それにしても、安く見られたものだ。
「仕事はもう終わったし、風俗で働いてるわけでもない」
「そうか、じゃあ今から飲みに行こうぜ。昔を思い出して楽しくさ」
私がいま、どんな目で一郎を見ているのか分かるはずもないだろう。
肩に提げたバッグを突き出して、私は言った。
「見て、以前のシャネルじゃない、ディスカウント店で買った安物のバッグ。いまの私の全てがこのバッグに入ってるの」
何を言わんとしているのか全く理解できないようすで、一郎は私を見た。
「毎日仕事を予約して、色んな現場でこき使われる日雇い派遣。それがいまの仕事」
あっけにとられている一郎は、かける言葉もないのだろう。黙ったまま、固まっていた。
「そして、ここのネカフェが私の今日のねぐら。世間ではネットカフェ難民なんて言われてるのよね」
隣のパチンコ屋が、盛大にボーナスゲームを謳って盛り上げている。派手なネオンが一郎の顔を赤く染めた。
きっと私の顔も赤く照らされているだろう。
いつのまにか頬を伝っている涙は、どんな風に彼に見えるのだろうか。
「飲みに誘うお金があるなら、私に頂戴よ」
一郎は何も答えなかった。いや、答えられないというのが正解だろうか。
「それが出来ないなら、二度と声を掛けないでね」
立ち尽くす一郎にきびすを返すと、雑居ビルのエレベーターに乗り込む。そして階数ボタンと、閉じるのボタンを素早く押した。
(さよなら……)
私は一郎と、自分の過去に別れを告げた。
「なんでそんなこと聞くの?」
「そりゃ心配してたからだよ」
電話もメールの一通もなしで、心配してたなどとよく言えたものだ。
「仕事……なにしてるんだ。もしかして、今から出勤か?」
この近くには夜の歓楽街もある。一郎の考えていることが分かると、その浅はかな想像にため息がもれた。
それにしても、安く見られたものだ。
「仕事はもう終わったし、風俗で働いてるわけでもない」
「そうか、じゃあ今から飲みに行こうぜ。昔を思い出して楽しくさ」
私がいま、どんな目で一郎を見ているのか分かるはずもないだろう。
肩に提げたバッグを突き出して、私は言った。
「見て、以前のシャネルじゃない、ディスカウント店で買った安物のバッグ。いまの私の全てがこのバッグに入ってるの」
何を言わんとしているのか全く理解できないようすで、一郎は私を見た。
「毎日仕事を予約して、色んな現場でこき使われる日雇い派遣。それがいまの仕事」
あっけにとられている一郎は、かける言葉もないのだろう。黙ったまま、固まっていた。
「そして、ここのネカフェが私の今日のねぐら。世間ではネットカフェ難民なんて言われてるのよね」
隣のパチンコ屋が、盛大にボーナスゲームを謳って盛り上げている。派手なネオンが一郎の顔を赤く染めた。
きっと私の顔も赤く照らされているだろう。
いつのまにか頬を伝っている涙は、どんな風に彼に見えるのだろうか。
「飲みに誘うお金があるなら、私に頂戴よ」
一郎は何も答えなかった。いや、答えられないというのが正解だろうか。
「それが出来ないなら、二度と声を掛けないでね」
立ち尽くす一郎にきびすを返すと、雑居ビルのエレベーターに乗り込む。そして階数ボタンと、閉じるのボタンを素早く押した。
(さよなら……)
私は一郎と、自分の過去に別れを告げた。