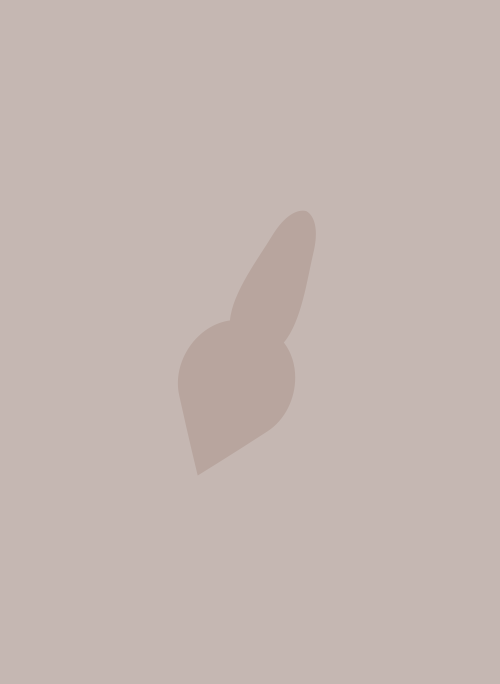そこで僕は、思い出す。
もうひとつの僕の習慣。
「あ。それなら
シューを起こしてきます。」
アルマさんの旦那さんは数年前に王都に徴兵され、そのまま戦争で亡くなった。母と子、ふたりきりのこの家。もうひとりの家族が、娘のシューだ。
僕がこうしてこの家で暮らしているのも、さらに、僕がまた話すことができるようになったのも、シューのおかげだった。
怪我の治った僕を、毎日毎日病院の外に連れ出し、明るく笑って話しかけ、そして村の子と遊ばせてくれた。
僕が初めて声を出して笑ったときは、村のだれよりも喜んでくれたのを覚えている。
「ああ、そのことなんだけど。
シューは今は出かけてるのよ。」
「出かけてる?」
僕はアルマさんの言葉に驚く。
毎朝、パンの仕込みが終わって、シューを起こしに行くのも、いつしか僕の習慣になっていた。
下手したら、昼まで起きてこないシューを起こすのは、はじめのころは、パンの仕込みを覚えるのよりも大変だった。最近は慣れてしまって、上手く起こせるようになったけど。
そのシューがこんな朝早くから、しかも僕が会わなかったということは、僕が起きるよりも早く、出かけたのだという。
「シューがこんなに早く起きるなんて珍しいですね。」
思わずそう言う僕にアルマさんは笑い、
「ふふ、そうね。
これでもイルトが来てからは早くなったほうよ。」
と言う。
「そうなんですか?」
「ええ。わたしも驚いてるの。
あのシューが毎朝毎朝嬉しそうに起きてくるんだから。
イルトもはじめはシューを起こすの大変だったでしょう?」
そう聞かれ僕は、初めてシューを起こしに行ったときのことを思い出して、ははっと笑った。あれから寝ぼけたシューのパンチをよけるのが上手くなったなんて、だれにも言えない。
そんなことを考え、僕はふっと笑う。
「もう慣れましたよ。」
「ふふふ。さすがね。」
と、そこで。