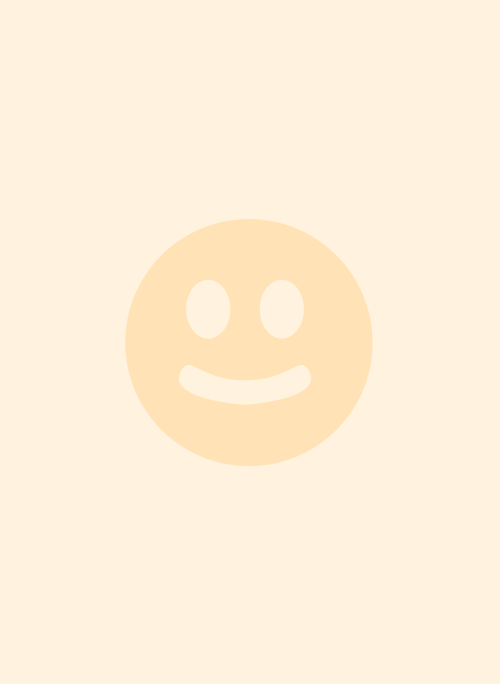「サツキさん」
「あたし嫌な奴なのよ。逃げるだけなら別に風俗じゃなくてもよかったのに」
嫌な奴なんかじゃないよ、て言いたかったけど
「そっか」
俺はひたすら聞くことにした。
「たくさんの男に触られたら、店長のことなんか特別じゃなくなるって思った。そこまでしなきゃ忘れられそうになかった。好きだった」
そんなに?俺は少し心臓的なものがチクッとしたけど
「うん」
先を促した。
「あたしはそこまでしたんだから、それでいいでしょ?てサキに対してあてつけみたいな気持ちもあった。サキは何も知らないのに」
「うん」
「それからはとにかく男の人を見下すばっかり。気持ちいいわけないのに、感じたフリすればバカみたいに興奮するし」
「…」
「ローション仕込んで喘ぎながら様子見て締め付けてぐったりすれば、満足するし」
俺は今、想像してたのと違うショックを受けています。
「男なんて、出せればそれでいいのよ」
否定できません。
「セックスなんか苦痛でしかない。何が楽しいのかわからない。でもあたしにはぴったりの仕事」
「…そんな」
サツキさんは無表情のまま、泣いている。
「サツキさん」
「仕事に慣れてから…何も考えないようにしてたのに…ちょっと思い出しちゃった。サキ、元気かなぁ。子供、可愛いんだろうなぁ」
「サツキさん」
「時間が経っても、何考えていいのかわかんないや」
サツキさんはタオルで顔をガシガシ拭きはじめた。
「…時間経ってないよ」
サツキさん、気付いて。
「きっと、いろんなとこが痛かったんでしょ?時間が経たなきゃ治らないのに、サツキさんは時間を止めてる」
「…」
サツキさんは顔を拭く手を止めた。
「ああしろ、こうしろなんて、俺は言えないけど。今のままじゃ、ずっと痛いよ」
サツキさんはタオルを膝に置いて、下を向いて小さい声で言った。
「うん、そうだね。でも別に、それでもいい」
!
「なんで!?」