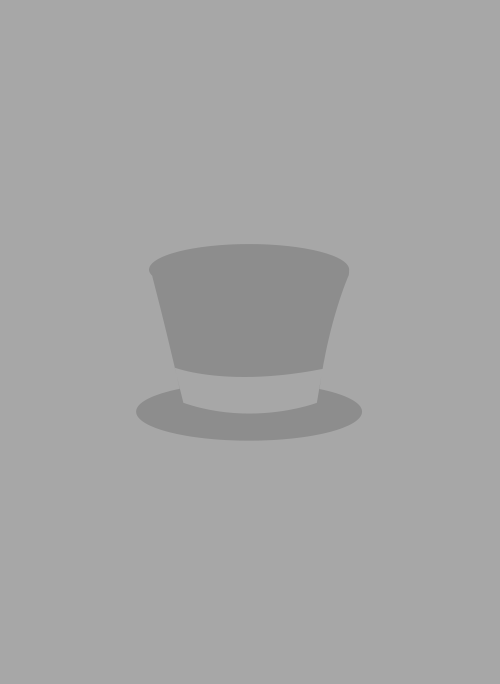あまりにも、ひどい言葉。
恵理夜の視線は、老人を責めていた。
「……それから何年も、桜が咲く季節になる度にワシはあいつを責めた。けれどあいつは変らぬ態度で微笑んでいた」
それが、その人にできる唯一のことなのだろう。
「……けれど、一昨年の春だ。夜中に喉が渇いて目覚めると、あいつは泣いておった。息子の仏壇の前で、両手を合わせて泣いておったのだ」
その人は、夫に責められ、そして自身でも責めていたのだろう。
何年も何年も、愛しい桜が咲く季節になる度に――
恵理夜の視線は、老人を責めていた。
「……それから何年も、桜が咲く季節になる度にワシはあいつを責めた。けれどあいつは変らぬ態度で微笑んでいた」
それが、その人にできる唯一のことなのだろう。
「……けれど、一昨年の春だ。夜中に喉が渇いて目覚めると、あいつは泣いておった。息子の仏壇の前で、両手を合わせて泣いておったのだ」
その人は、夫に責められ、そして自身でも責めていたのだろう。
何年も何年も、愛しい桜が咲く季節になる度に――