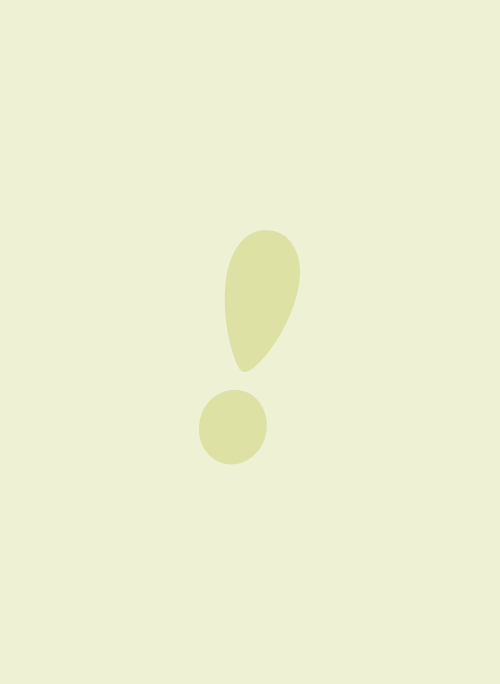「せんせぇ〜……ま、まだ走るんですかぁ〜?」
「あと5分な」
生徒達の顔には疲れの色が見え、足元は若干おぼつかなくなってきたようだ。
「えぇ〜!?もう限界〜ッ」
「お前ら若いんだから20分くらい走れるだろうが」
ぜーぜーと息を切らせながら不満を垂れる生徒達を、ストップウォッチを眺めながら軽くあしらう。
「先生も走ってみろって……!」
「馬鹿にするなよ。俺は走れる」
ストップウォッチを地面に置き、生徒達に混ざって俺も走りだした。
俺が学生の頃は体育といえばとりあえず走らされていたな。
それに比べてゆとり教育だなんだと甘やかされて育った最近の若者は鍛え方が足りない。
授業終了のチャイムとともに全員が走るのをやめ、簡単に挨拶を済ませると各自教室へと戻って行った。
まだまだ走れない事もなかったが、このところの運転不足がたたって流石に息があがってしまった。
10代の子供達といると、自分ももう若くないな、なんて思ってしまう。
「あ……ッちぃ」
元々走る予定は無かったからタオルなんて気が利いた物は持っていなくて、Tシャツの裾を持って汗を拭った。
「黒澤先生」
呼ばれて声がした方を振り返るとそこには小春が立っていた。
その手には可愛らしい絵柄がプリントされたタオルが握られている。
「葵兄って運動できるんだ?」
「当たり前だろ。通知表の中で体育が一番良かったんだから。つーか俺、体育教師だしな」
「ぼーっとしてるから運動神経ニブイのかと思ってた」
小春はからかうような視線を向けて笑うと、手にしていたタオルを投げて寄越した。
「葵兄、ちょっと格好よかったよ!」
それだけ言うと「じゃあねッ」と、手を振りながら走り去ってしまった。
残された俺はというと。
「反則だろ……その笑顔……!」
一瞬で赤くなった顔をタオルで覆い隠さずにはいられない。